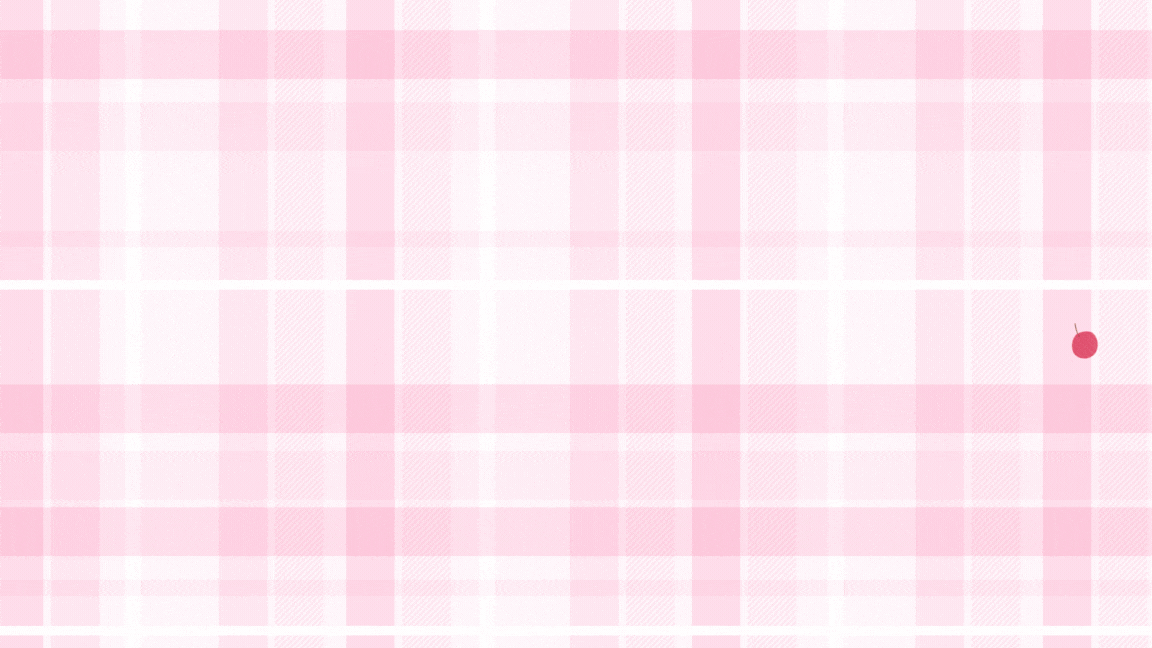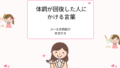「寒の入り」という言葉、寒い季節に使う言葉ですが、聞いたことはありますか?「寒の入り」の時期はいつ?どんな意味があるの?と思ったことはありませんか?この記事では、「寒の入り」の意味や、メール文例と1月〜2月の時期に使える季節の言葉を例文とともに詳しく解説します。ビジネスシーンやプライベートでも使えるように、時候の挨拶の基本も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
「寒の入り(かんのいり)」とは?意味と時期
「寒の入り(かんのいり)」とは、二十四節気(にじゅうしせっき)の「小寒(しょうかん)」の初日のことです。二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたものです。
小寒は冬の6つの節気の5番目で、冬至と大寒の間に位置します。「寒の入り」は、毎年1月5日頃にあたります。この日から立春(2月4日頃)までの約30日間を「寒中」と呼び、冬の寒さが最も厳しい時期となります。
「寒の明け」とは、冬の寒さが終わり、春に向かう時期を指します。「大寒」の最終日2月3日頃を指します。寒の明けが終わると、暦の上では「立春」(りっしゅん)となり、春が始まります。

↑「寒の入り」と「寒の明け」をまとめました♡
寒の入りの使い方と季節の言葉
「寒の入り」は、手紙や挨拶状などで季節を表す言葉として使うことができます。特に、1月〜2月の寒い時期に相手の安否や健康を気遣う際に用いるのが一般的です。ここでは、「寒の入り」を使った季節の言葉と例文をご紹介します。

【時候の挨拶】
・寒の入りとなり、本格的な冬の到来を感じます。
・寒の入りを過ぎ、日増しに寒さが厳しくなってまいりました。
・寒の入りを迎え、一段と寒さが厳しくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
・寒の入りを過ぎ、風邪などひかれていませんでしょうか。
・寒の入りを迎えましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
・寒の入りとなり、寒さが厳しくなりましたので、どうぞご自愛ください。
・寒の入りを迎えました。皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
・寒の入りとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください。(メールの結び)

↓時候の挨拶とは?参考にしてみてください。
時候の挨拶とは?
手紙や挨拶状の冒頭で、季節や天候に応じた言葉を用いて相手の安否や健康を気遣うものです。
・季節を表す言葉(例:寒の入り、厳寒、初春など)
・相手の安否や健康を気遣う言葉(例:いかがお過ごしでしょうか、ご健勝のこととお慶び申し上げますなど)
・こちらの様子を伝える言葉(例:おかげさまで元気に過ごしております、寒さ厳しき折からご自愛くださいなど)
「寒の入り」を使ったメール文例:ビジネスメール
ビジネスメールでは、以下1)〜3)のように「寒の入り」の挨拶を用いると良いです。
1)用件のついでに:何か用件があり、そのメールの締めに季節の挨拶として「寒の入りを迎えましたが、〇〇様におかれましては、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます」と付け加える。
2)季節の話題に触れる:メールの冒頭で「寒の入りとなり、一段と寒さが厳しくなってまいりました」のように季節の話題に触れ、そこから本題に入る。
3)寒中見舞いに使う

↓寒中見舞いの文例です♡
〇〇会社〇〇様
件名: 寒中お見舞い申し上げます
拝啓
寒の入りを迎え、寒さも一段と厳しくなってまいりました。貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
さて、寒さが厳しい折、貴社の皆様におかれましてはお健やかにお過ごしでしょうか。
弊社一同も、体調管理に十分留意しつつ、業務に励んでおります。
本年も変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいますよう、心よりお祈り申し上げます。
敬具
△△ △△
「寒の入り」を使ったメール文例:プライベート(目上の人)
寒の入りは、冬の寒さが本格化する時期を表す言葉で、1月5日頃から立春までの期間を指します。この時期に合わせたメールの文例を紹介します。
基本的な挨拶メール
件名:寒の入りの折、ご自愛くださいませ
拝啓
寒の入りを迎え、ますます寒さが厳しくなってまいりました。
〇〇様におかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。
厳しい寒さが続く中、どうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
またお目にかかれる日を楽しみにしております。
敬具
お礼を伝えるメール
件名:寒の入りの折、お礼申し上げます
拝啓
寒の入りを迎え、冷え込みの厳しい日が続いておりますが、〇〇様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。
先日はお心のこもったお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。温かいお言葉に心より感謝申し上げます。
寒さ厳しき季節ですので、どうかご自愛のほどお祈り申し上げます。
またお会いできる日を楽しみにしております。
敬具
体調を気遣うメール
件名:寒の入りの折、ご自愛くださいませ
拝啓
寒の入りの候、寒さが一層厳しくなってまいりました。〇〇様にはお元気でお過ごしでしょうか。
この時期は体調を崩しやすい季節でもございますので、どうかご無理をなさらず、ご自愛くださいませ。
お忙しいとは存じますが、どうぞお身体を大切にお過ごしください。
またお目にかかれる日を楽しみにしております。
敬具

↓ここでのポイント♡
・冒頭の季節の挨拶に「寒の入り」を自然に組み込むことで、形式的になりすぎず季節感が伝わります。
・目上の方への敬意を忘れずに、「ご自愛ください」「お変わりなくお過ごしのことと存じます」などの丁寧な表現を意識しましょう。
1月~2月に使える季節の言葉と例文
季節感を意識した言葉遣いは、挨拶文やメールに温かみと礼儀正しさを感じさせます。
1月に使える季節の言葉↓
新春(しんしゅん)
使用期間:1月1日~1月中旬(松の内までが目安)
意味:新しい年の始まりを祝う言葉
例文:新春のお慶びを申し上げます。
迎春(げいしゅん)
使用期間:1月1日~1月7日(松の内まで)
意味:新年を迎えることを祝う言葉
例文:迎春の候、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
初春(しょしゅん・はつはる)
使用期間:1月1日~1月末頃まで
意味:春の初めの時期を指す言葉です
例文:初春の候、ますますのご健勝をお祈り申し上げます。
寒中(かんちゅう)
使用期間:1月5日頃(小寒)~2月3日頃(立春前日)
意味:一年で最も寒さが厳しい時期を指す
例文:寒中の候、皆様のご健康を心よりお祈りいたします。
新春(しんしゅん)
使用期間:1月1日~1月中旬(松の内までが目安)
意味:新しい年の始まりを祝う言葉
例文:新春のお慶びを申し上げます。
2月に使える季節の言葉↓
立春(りっしゅん)
使用期間:2月4日頃~2月中旬まで
意味:暦の上で春の始まりを指す
例文:立春とは名ばかりの寒さが続いております。
余寒(よかん)
使用期間:2月4日(立春)以降~2月末頃まで
意味:立春を過ぎても続く寒さのこと
例文:新春のお慶びを申し上げます。
早春(そうしゅん)
使用期間:2月中旬~3月初旬
意味:春の訪れを感じ始める頃
例文:早春の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
春寒(しゅんかん)
使用期間:2月下旬~3月初旬
意味:春先の寒さ
例文:春寒の折、くれぐれもお身体にお気をつけください。
まとめ
「寒の入り」の意味や時期、使い方について解説しました。「寒の入り」は、1年で最も寒い時期の始まりを表す言葉であり、手紙や挨拶状などで季節を表す言葉として使うことができます。例文を参考に、ぜひ「寒の入り」を使った季節の言葉を使ってみてください。