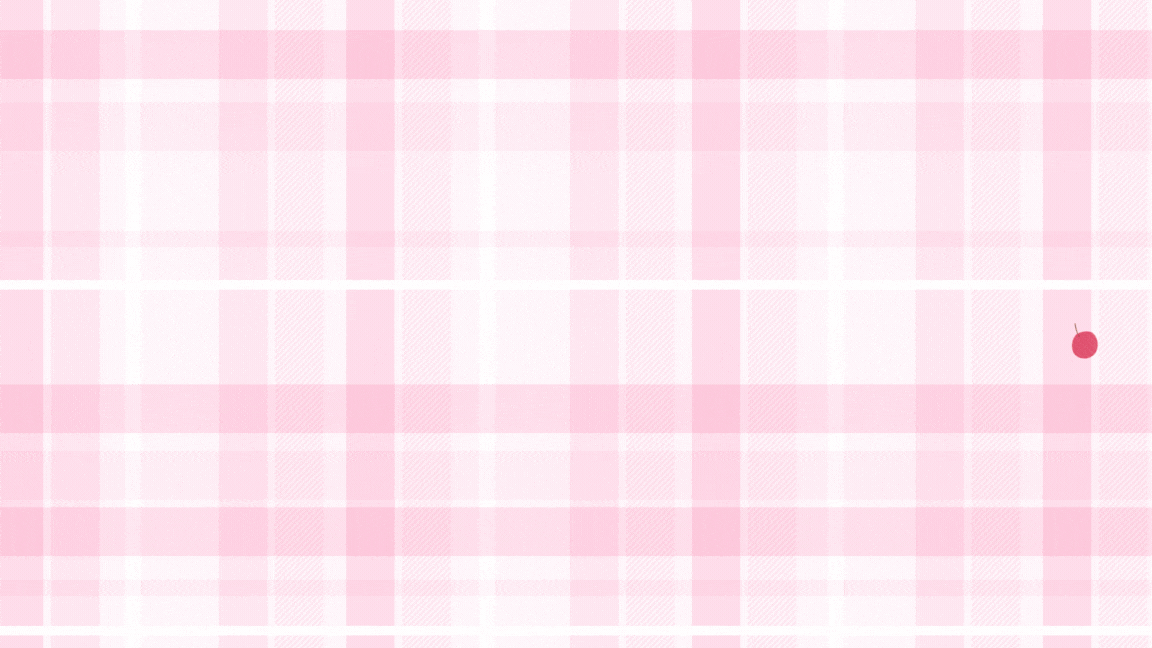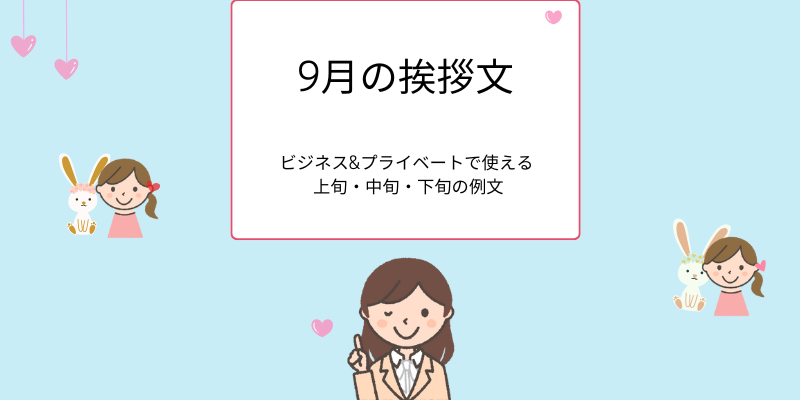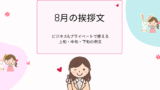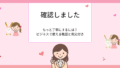9月は、暑さが和らぎ始め、秋の気配を感じる季節です。敬老の日やお彼岸、運動会などの行事も多く、季節の移ろいを感じられる時期でもあります。ビジネスシーンでは、残暑をいたわる言葉や業務への配慮を添えると好印象に。プライベートでは、夏の思い出や秋の楽しみを交えた一言が、自然なやりとりのきっかけになります。この記事では、9月上旬・中旬・下旬に分けて使える挨拶文例を、ビジネス向けからカジュアルな表現まで幅広くご紹介します。ぜひ、9月の挨拶文を作成する際の参考にしてください。
9月時候の挨拶一覧

9月は、残暑が続く一方で、朝夕には涼しさが増し、秋の訪れを感じられる季節です。「初秋」「長月」「秋分」「お彼岸」「台風の季節」など、9月ならではの言葉を挨拶に取り入れることで、相手に季節感を伝えやすくなります。
ビジネスメールでは、体調を気遣う残暑見舞いや、秋の業務に向けた励ましの一言が効果的です。プライベートでは、夏の出来事や秋の予定に触れることで、会話が広がりやすくなります。
時候の挨拶は、気候の変化や季節の情緒を表現するための大切な言葉です。使うタイミングは明確に区切れない場合もありますが、以下に9月上旬・中旬・下旬ごとの目安をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
| 時候の挨拶 | 意味 | 使用時期の目安 |
| 処暑の候 (しょしょのこう) | 処暑を迎え、暑さのピークを越えた頃のご挨拶。 | 8月23日〜9月7日頃 |
| 残暑の候 (ざんしょのこう) | 立秋を過ぎても暑さが続く時期に用いるご挨拶。 | 8月23日〜9月7日頃 |
| 初秋の候 (しょしゅうのこう) | 暑さが少しずつ和らぎ、秋の始まりを感じるご挨拶。 | 8月上旬〜9月7日頃 |
| 野分の候 (のわきのこう) | 台風など、野の草を吹き分ける強い風が吹く時期のご挨拶。 | 9月1日〜9月10日頃 |
| 秋涼の候 (しゅうりょうのこう) | 夏の暑さが和らぎ、秋らしい涼しさが感じられるようになった頃のご挨拶。 | 9月7日〜10月6日頃 |
| 白露の候 (はくろのこう) | 大気が冷え、草木に朝露が降り始める時期のご挨拶。二十四節気の「白露」から使用。 | 9月7日〜9月22日頃 |
| 重陽の候 (ちょうようのこう) | 菊の節句である「重陽の節句」(旧暦9月9日)の頃のご挨拶。菊の花が咲き、長寿を願う時期に使われます。 | 9月9日 |
| 仲秋の候 (ちゅうしゅうのこう) | 旧暦の8月、つまり秋の真ん中の時期のご挨拶。 | 9月10日〜10月10日頃 |
| 秋晴の候 (しゅうせいのこう・あきばれのこう) | 空が高く澄み渡り、心地よい晴れの日が続く時期のご挨拶。 | 9月上旬〜10月22日頃 |
| 秋雨の候 (しゅううのこう) | しとしとと静かに降り続く、秋の長雨の時期のご挨拶。日本の秋の気候を伝える言葉です。 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 秋分の候 (しゅうぶん) | 昼と夜の長さがほぼ同じになる「秋分の日」の頃のご挨拶。この日を境に、本格的な秋へと季節が進みます。 | 9月23日〜10月8日頃 |
| 秋月の候 (しゅうげつのこう) | 空に浮かぶ月が美しく、お月見が楽しめる時期のご挨拶。 | 9月下旬〜10月上旬 |
9月上旬の挨拶文
9月上旬は、残暑が厳しい日が続く一方で、朝夕には少しずつ涼しさが感じられる時期です。台風シーズンの始まりでもあり、天候の変化に気を配る必要があります。防災の日や新学期の始まり、敬老の日を控えたこの時期には、相手の体調を気遣いつつ季節感を取り入れた挨拶が好印象につながります。ビジネスでは残暑をいたわる表現を、プライベートでは夏の思い出や秋の予定に触れる表現を心がけると良いでしょう。
9月上旬の挨拶文のポイント
時候の挨拶:「初秋の候」「新涼の候」「初秋のみぎり」「新秋の候」などがよく使われます。まだ残暑が続く場合には「残暑の候」も適切です。9月上旬は立秋を過ぎているため、「盛夏」は避け、秋を意識した表現に切り替えるのが自然です。
季節の話題:台風、朝夕の涼しさ、秋の虫の声、新学期の始まり、防災の日、重陽の節句、秋の味覚(梨やぶどう)、秋祭りの準備、十五夜など、夏から秋への移り変わりを感じさせる話題を取り入れると良いでしょう。
気遣いの言葉:残暑による体調への配慮や、台風・大雨への注意を促す言葉が効果的です。また、新しい生活や業務が始まる時期でもあるため、励ましや応援の一言を添えると丁寧で心のこもった印象をになります。

少しずつですが風が涼しくなってきますね。

涼しくなってきた時の言葉をおさえましょう♡
ビジネス向け例文
ビジネスシーンでは、9月上旬にふさわしい時候の挨拶を使いながら、相手の体調や業務への配慮を伝えることが大切です。ここでは、フォーマルな漢語調と、社内や親しい取引先に向けた口語調に分けて、9月上旬に使える挨拶文例をご紹介します。
書き出しの例文【漢語調:フォーマルな場面や目上の人へ】
「初秋の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
解説:まだ残暑が残る9月上旬にふさわしい、一般的で丁寧な書き出しです。相手の発展を願う気持ちを伝える季節の挨拶です。
「新秋の候、皆様にはますますご健勝のことと拝察いたします。」
解説:「新秋」は秋の初めを意味する表現。季節感を示しつつ、相手の健康を願うフォーマルな書き出しです。
「残暑の候、皆様にはお変わりなくご活躍のことと存じます。」
解説:暦の上では秋ですが、残暑が続く9月上旬に使える表現です。相手の安否と活躍を気遣う言葉を加えることで、より丁寧な印象になります。メール・文書どちらにも使えます。
結びの例文【漢語調:フォーマルな場面や目上の人へ】
9月上旬の季節感にふさわしい、フォーマルな結びの例文です。
「残暑厳しき折、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」
解説:厳しい残暑を踏まえて、体調への配慮と相手の幸せを願う丁寧な締めくくりです。
「初秋のみぎり、くれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。」
解説:9月上旬の時期に自然に使える、気遣いある表現です。
「秋の気配が感じられますが、引き続きご活躍されますことをお祈り申し上げます。」
解説:季節の変わり目に触れ、相手の活躍を願う丁寧な締めくくりです。
書き出しの例文【口語調:社内、親しい取引先など】

親しい人やちょっとした時に使える相手を気遣える例文です♡
「残暑が続いていますが、〇〇さんはいかがお過ごしでしょうか。」
解説:親しみやすく、少し柔らかい印象のカジュアルな書き出しです。
「お疲れ様です。少しずつ涼しくなってきましたが、引き続き暑い日が続いております。どうぞご無理なさいませんように。」
解説:朝夕の涼しさに触れつつ、引き続きの暑さを気遣う自然な季節の挨拶です。社内メールなどに向いています。
「いつもお世話になっております。朝晩は過ごしやすくなりましたが、日中はまだまだ残暑が厳しいですね。〇〇さんはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:朝晩の涼しさ、日中の残暑の両方に触れ、相手の体調を気遣う親しみやすい表現です。
結びの例文【口語調:社内、親しい取引先など】
「残暑が厳しいですが、どうぞ健やかにお過ごしください。」
解説:相手の健康を願う、丁寧な結びです。
「秋の長雨や残暑で体調を崩しやすい時期ですので、どうぞお身体にお気をつけてお過ごしください。」
解説:天候の変化にも配慮した、気遣いのある結びです。親しい関係性で、メールや手紙、チャットで用いる際に適しています。
「少しずつ秋の気配が感じられる頃となりました。どうぞご自愛ください。」
解説:季節の移り変わりを伝えつつ、相手の体調を気遣う季節の挨拶です

↓書き出し部分から本文へのつなぎ(例)も参考にしてください♡
・「残暑の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、〜」
解説:9月上旬の季語である「残暑の候」を用いて、時候の挨拶を述べた後、本題に入ります。
・「秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いておりますが、〜(本文)〜」
解説:暦の上では秋であるものの、実際には厳しい暑さが残る9月上旬にぴったりの、相手を気遣う一文です。
・「初秋の候、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。早速ではございますが、〜」
解説:「晩夏」という言葉で季節感を出しつつ、丁寧な表現で相手への敬意を示します。
・「日頃は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。〜(本文)〜」
解説:時候の挨拶を省略し、日頃の感謝を伝えてから本題に入る、簡潔で丁寧な書き出しです。
プライベート向け例文
プライベートな手紙やメッセージでは、よりパーソナルな季節の話題や、相手の状況に合わせた温かい言葉を盛り込むと良いでしょう。残暑、秋の気配、台風、中秋の名月など、9月上旬の季節の話題に触れる言葉を盛り込むと、より情緒豊かな挨拶文になります。
書き出しの例文
「厳しい残暑が続いていますが、〇〇さんはお元気にお過ごしですか?」
解説:夏の終わりを感じさせる言葉で、相手の近況を柔らかく尋ねます。
「風の中に、ふと金木犀の香りが漂う季節となりました。〇〇さんはお変わりないでしょうか。」
解説:秋の訪れを感じさせる描写からはじまる、柔らかく優しいトーンの季節の挨拶です。
「朝晩は少し涼しくなりましたが、お変わりありませんか。」
解説:季節のわずかな変化を共有し、相手の体調をさりげなく気遣う書き出しです。
結びの例文
「残暑が続きますが、どうぞご無理なさらないでくださいね。」
解説:相手の健康を気遣う、心温まる結びの言葉です。
「夏の疲れが出やすい頃ですので、どうぞご自愛ください。」
解説:相手の体調への配慮がしっかり伝わる、あたたかい締めの言葉です。
「実りの秋、おいしいものをたくさん食べて、元気に過ごしてくださいね。」
解説:秋の季節感をしっかり取り入れつつ、ポジティブな結びになります。

↓以下のテンプレートは、目上の人や親しい間柄に使ってみてください♡
残暑が続く毎日ですが、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。朝夕は少し涼しい風が感じられるようになりましたが、季節の変わり目ですので、くれぐれもご無理なさらないでください。どうぞご自愛ください。
〇〇様、ご無沙汰しております。
立秋を過ぎ、ようやく暑さも峠を越えたように感じられる頃となりました。〇〇様におかれましては、夏の疲れなど出ていませんでしょうか。日中はまだ暑い日もございますので、どうぞご無理なさらないでください。
9月中旬の挨拶文

9月中旬は、まだ日中は残暑が厳しいものの、朝夕には涼しい風が感じられ、少しずつ秋へと移り変わる季節です。十五夜のお月見やお彼岸など、秋らしい行事も増え、自然の移ろいを感じやすい時期でもあります。ビジネスやプライベートでの挨拶文では、残暑への気遣いとともに、秋の始まりを喜ぶ言葉を添えることで、季節感のある丁寧な表現になります。
9月中旬の挨拶文のポイント
時候の挨拶:「仲秋の候」「白露の候」「秋分の候」などが適切です。「仲秋」は旧暦8月を指しますが、現代では9月中旬から下旬にかけて広く使われます。「白露」は二十四節気のひとつで、朝露が降り始める頃を表します。
季節の話題:中秋の名月、月見、秋分の日、お彼岸、紅葉の始まり、秋の味覚(栗、さんま)、稲穂の実り、澄んだ秋の空、日没の早まりなど、長月、秋の情緒を感じさせる話題を取り入れると、より季節感が出ます。
気遣いの言葉:季節の変わり目による体調の変化への配慮や、寒暖差への注意を促す言葉などを添えると、相手への気遣いが伝わります。「寒暖差にご留意ください」「季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください」などの言葉を添えると丁寧です。

日ごとに秋が深まってきますね♡
ビジネス向け例文
ビジネスシーンでは、形式的な時候の挨拶を用いながらも、相手への敬意や体調への気遣いを含めるのが基本です。9月中旬は、秋分の日やお彼岸を迎える時期で、残暑と秋の気配が入り混じる季節感を表現できます。以下にフォーマル(漢語調)とカジュアル(口語調)に分けて、ビジネスメールや手紙で使える例文をご紹介します。
書き出しの例文【漢語調:フォーマルな場面や目上の人へ】
「秋分の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。」
解説:秋分の日(9月23日ごろ)を中心とした季節にふさわしい表現で、相手の繁栄を願う丁寧な季節の挨拶です。
「秋分の候、皆様におかれましては一段とご活躍のことと存じます。」
解説:9月下旬の秋分(9月23日頃)を過ぎてから使える表現です。日ごとに秋が深まる時期に、相手の安否と活躍を気遣う言葉を加えることで、より丁寧な印象になります。メール・文書どちらにも使えます。
「仲秋の候、皆様にはますますご清祥のことと拝察いたします。」
解説:9月中旬〜下旬にふさわしい「仲秋」を用いた表現。暑さが和らぎ、秋の涼しさを感じる時期に適した挨拶。体調を気遣うニュアンスがあり、ビジネス文書に使いやすい季節の挨拶です。
結びの例文【漢語調:フォーマルな場面や目上の人へ】
9月下旬の時期にふさわしい、フォーマルな場面や目上の人へ向けた結びの例文です。
「秋分を迎え、日ごとに涼しさが増しております。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。」
解説:秋分を踏まえた時期に適した、丁寧で品のある結びです。
「朝晩の冷え込みが感じられる折、どうぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。」
解説:体調への気遣いを前面に出した締め方で、ビジネスメールでも使いやすい表現です。
「秋冷の折、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」
解説:秋の涼しさ、そして少しずつ冷え込む時期を踏まえて、体調への配慮と相手の幸せを願う丁寧な締めくくりです。
「秋冷のみぎり、くれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。」
解説:秋の涼しさ、そして少しずつ冷え込む時期を踏まえた丁寧な表現。文書やメールの終わりに自然に使える、気遣いある表現です。

秋冷(しゅうれい)とは秋になって感じる涼しさのことです♡
書き出しの例文【口語調:社内、親しい取引先など】
「すっかり秋らしくなってまいりましたが、〇〇様はいかがお過ごしでしょうか。」
解説:親しみやすく、少し柔らかい印象のカジュアルな書き出しです。
「お疲れ様です。朝晩は冷え込むようになりましたが、体調を崩されていませんか?」
解説:季節の変わり目に向けた体調への気遣いを伝える、社内メールなどに向いている表現です。
「お疲れ様です。秋分を迎え、過ごしやすい日が増えてまいりましたね。」
解説:秋分前後の季節感を取り入れた、社内メールなどに適した表現です。
「いつもお世話になっております。日中は暑さが残るものの、秋の気配が感じられる頃となりました。」
解説:残暑と秋の移ろいを同時に盛り込み、9月中旬らしい季節の挨拶です。
結びの例文【口語調:社内、親しい取引先など】
「朝晩の冷え込みが強くなってまいりましたので、どうぞお体にお気をつけください。」
解説:体調を気遣うやわらかな表現。取引先にも安心して使える挨拶です。
「季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ですので、くれぐれもご自愛くださいませ。」
解説:秋らしい季節の注意点を盛り込み、相手を思いやる締めくくりです。
「秋分を迎え、実り多い季節となりました。今後ますますのご活躍をお祈りしております。」
解説:秋の行事や情緒を絡めながら、相手の活躍を願うポジティブな結びです。
「秋の長雨で肌寒い日が続きますので、どうぞご自愛ください。」
解説:秋ならではの天気に触れ、相手の体調管理を具体的に気遣う表現です。

↓書き出し部分から本文へのつなぎ(例)です♡
「さて、朝夕は涼しくなってまいりましたが、〜(本文)〜」
「秋分の折、誠に恐縮ではございますが、〜(本文)〜」
「秋涼の候、皆様には変わらずご健勝のことと存じます。さて、〜」
「日頃より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。早速ではございますが、〜」
プライベート向け例文
プライベートな手紙やメッセージでは、季節の移ろいや身近な出来事に触れることで、より温かみのある挨拶文になります。9月中旬は、日中の暑さが残る一方で、朝夕には秋の涼しさを感じる時期です。彼岸や十五夜、秋の味覚といった話題を盛り込むと、季節感が伝わりやすく、相手に寄り添った文面になります。
書き出しの例文
「朝晩はだいぶ涼しくなりましたね。〇〇さんは変わらずお元気にされていますか。」
解説:夏から秋への移ろいを感じさせつつ、相手の近況を自然に尋ねる表現です。
「朝晩に少し秋の気配を感じるようになりました。涼しさに助けられつつ過ごしています。」
解説:自然の変化を取り入れ、落ち着いた雰囲気の書き出しです。
「日中はまだ汗ばむ陽気ですが、秋の虫の音が心地よく感じられる頃になりましたね。」
解説:残暑と秋の気配を対比させ、情緒を伝える柔らかな書き出しです。
「今年もお彼岸の季節となりました。ご家族の皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:彼岸という行事に触れながら、相手を思いやる落ち着いた挨拶です。
「そろそろ十五夜の季節ですね。今年は月見団子を用意して夜空を眺めたいと思っています。」
解説:季節行事を話題にすることで、親しみやすく会話につながる書き出しです。
結びの例文
「食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋…〇〇さんにとって素敵な秋になりますように。」
解説:前向きな余韻を残しつつ、今後のやり取りを促す結びの表現です。
「涼風が心地よい季節、素敵な秋の思い出がたくさんできますように。」
解説:秋らしい表現で、前向きな余韻を残す結びです。
「秋の味覚も楽しみな季節ですね。また近況をお聞かせいただければ嬉しいです。」
解説:季節の楽しみを共有しつつ、今後の交流を促す結びの表現です。

↓以下のテンプレートは、目上の人や親しい間柄に使ってみてください♡
秋気いよいよ深まる頃となりましたが、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。日中はまだ暑さが残る日もございますので、どうぞご無理なさらずお過ごしください。朝夕の寒暖差が大きくなりますので、ご自愛くださいませ。
〇〇様、ご無沙汰しております。
秋分の日も近づき、澄んだ空に浮かぶ月が美しい季節となりました。〇〇様におかれましては、お変わりなくお元気でいらっしゃいますでしょうか。どうぞ季節の変わり目、お身体にお気をつけください。
9月下旬の挨拶文

9月下旬は、秋分の日を境に昼夜の長さがほぼ同じになり、朝晩の涼しさも増して秋らしさが一段と深まる時期です。お彼岸や紅葉の便りが始まるなど、季節の移ろいを感じられる頃でもあります。ビジネスやプライベートでの挨拶文には、秋の情緒を取り入れながら、相手の健康や日々の生活を気遣う言葉を添えることが大切です。
9月下旬の挨拶文のポイント
時候の挨拶:「秋分の候」「秋雨の候」「秋月の候」などがよく使われます。秋分の日(9月23日ごろ)以降は、残暑ではなく涼しさや秋の深まりを感じさせる表現に切り替えるのが適切です。
季節の話題:涼しい風、爽やかな秋空、澄んだ月、彼岸花、秋の虫の声、紅葉の始まり、読書の秋、スポーツの秋など、秋本番の話題を取り入れると季節感が出ます。
気遣いの言葉:過ごしやすい気候になったことへの喜びを分かち合う言葉や、季節の変わり目による体調の変化への配慮を伝えると、相手への気遣いが伝わります。
ビジネス向け例文
ビジネスシーンでは、形式的な時候の挨拶を用いながらも、秋の深まりを感じさせる表現や、季節の変わり目の体調への気遣いを添えるのが基本です。ここでは、9月下旬にふさわしい挨拶文を、フォーマルな漢語調と、親しみやすい口語調に分けてご紹介します。
書き出しの例文【漢語調:フォーマルな場面や目上の人へ】
「秋冷の候、皆様にはお変わりなくご活躍のことと存じます。」
解説:秋が深まり、冷え込みが感じられる時期に使える表現です。気温の変化が大きくなる時期だからこそ、相手の安否と活躍を気遣う言葉を加えることで、より丁寧な印象になります。メール・文書どちらにも使えます。
「爽秋の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
解説:秋晴れの空が広がる爽やかな時期にふさわしい、一般的で丁寧な書き出しです。相手の発展を願う気持ちを伝えます。
「秋涼の候、皆様におかれましてはますますご清栄のことと拝察いたします。」
解説:朝夕が涼しく感じられる季節にふさわしい言葉で、相手の健康や繁栄を気遣う丁寧な表現です。

「爽秋(そうしゅう)の候」は9月中。「秋涼(しゅうりょう)の候」は10月7日ころ迄使えます♡
結びの例文【漢語調:フォーマルな場面や目上の人へ】
9月下旬の時期にふさわしい、フォーマルな場面や目上の人へ向けた結びの例文です。
「日増しに秋冷の折、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」
解説:日に日に寒さが増していくことを踏まえ、体調への配慮と相手の幸せを願う丁寧な締めくくりです。
「秋冷の折、皆様のご繁栄とご健康をお祈り申し上げます。」
解説:秋の深まりを感じさせる言葉を用いた、締めくくりに適した表現です。
「季節の変わり目でございますので、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。」
解説:秋口の体調変化に配慮し、相手の健康を願う丁寧な結びです。
「秋分のみぎり、今後のさらなるご発展を祈念申し上げます。」
解説:秋分を踏まえつつ、未来の発展を願うビジネス向けの結び言葉です。
書き出しの例文【口語調:社内、親しい取引先など】
「お彼岸を迎え、秋らしい気候となりましたが、体調など崩されておりませんでしょうか。」
解説:お彼岸の行事に触れ、相手を気遣う自然な挨拶です。
「すっかり秋らしくなってまいりましたが、〇〇さんはいかがお過ごしでしょうか。」
解説:親しみやすく、少し柔らかい印象のカジュアルな書き出しです。
「日中はまだ暑さが残りますが、朝夕は過ごしやすくなってまいりましたね。」
解説:残暑と秋の気配の両方を表現でき、社内メールなどに向いています。
結びの例文【口語調:社内、親しい取引先など】
「秋の夜長、どうぞ健やかにお過ごしください。」
解説:日没が早くなる時期に触れつつ、丁寧な結びの表現です。
「日中と朝晩の寒暖差が大きいので、どうぞお身体にお気をつけください。」
解説:具体的な気候の変化に触れ、相手の体調管理を気遣う表現です。
「実りの秋、おいしいものをたくさん食べて、この季節を楽しんでくださいね。」
解説:秋の味覚にふれた、より親しい関係性で使える結び言葉です。メールやチャットで用いる際に適しています。
プライベート向け例文
プライベートな手紙やメッセージでは、相手の近況に寄り添いながら、9月下旬ならではの秋の季節感や行事(秋分の日・お彼岸・お月見・台風・紅葉の始まり)に触れると温かみが増します。少しずつ涼しさを感じる頃ですので、「体調管理」や「秋の楽しみ」に関する言葉を添えると、情緒豊かで心のこもった挨拶文になります。
書き出しの例文
「彼岸花が咲き始め、秋の訪れを感じる頃となりました。〇〇さんはお変わりなくお過ごしですか。」
解説:季節の移ろいを描写しつつ、相手の近況を尋ねる自然な書き出しです。
「秋分の日も過ぎ、日暮れが早くなってきました。虫の声に耳を傾けながら過ごすのも心地よいものですね。」
解説:秋分の日、虫の声へとやわらかいトーンの季節の挨拶です。
「お月見の季節ですね。今年は月がとてもきれいに見えました。〇〇さんはご覧になりましたか。」
解説:秋ならではの行事を話題にし、共感を誘う親しみやすい書き出しです。
結びの例文
「秋の夜長をゆっくりお過ごしくださいね。また近況を聞かせてください。」
解説:「秋の夜長」など季節のキーワードを取り入れつつ、今後のやり取りを促す結びです。
「朝晩は冷え込みますので、どうぞご無理なさらず、ご自愛ください。」
解説:体調への配慮がしっかり伝わる、あたたかい締めの言葉です。
「台風の季節でもありますので、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。」
解説:9月下旬らしい注意喚起を盛り込みつつ、相手を思いやる締めの挨拶です。

↓以下のテンプレートは、目上の人や親しい間柄に使ってみてください♡
秋分の日を過ぎ、朝夕はすっかり涼しくなりました。〇〇様にはお健やかにお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。季節の変わり目ですので、どうぞご自愛くださいますようお祈り申し上げます。
〇〇様、ご無沙汰しております。
彼岸花が見頃を迎え、秋の深まりを感じる季節となりました。〇〇様におかれましては、お変わりなくお過ごしでしょうか。どうかお体を大切に、実り豊かな秋をお楽しみください。
まとめ
9月に入り、朝夕は少しずつ涼しさが感じられるようになりましたが、日中はまだ残暑が厳しい日も続きます。季節の変わり目は体調を崩しやすいため、ビジネスメールや手紙、プライベートなやり取りにおいても、相手を気遣う挨拶文を添えることが大切です。
この記事では、9月上旬・中旬・下旬の時期ごとに使える時候の挨拶や例文 をご紹介します。ビジネスシーンで好印象を与える丁寧な文例から、親しい人に送れるカジュアルな挨拶まで幅広くまとめました。
また、季節を感じさせる「長月」「初秋」「秋涼」などの言葉や、相手の健康や今後の実りを願う結びの表現もあわせて解説しています。ぜひ本記事を参考に、9月ならではの挨拶文・時候の挨拶 を取り入れ、相手に心のこもったメッセージを届けてみてください。