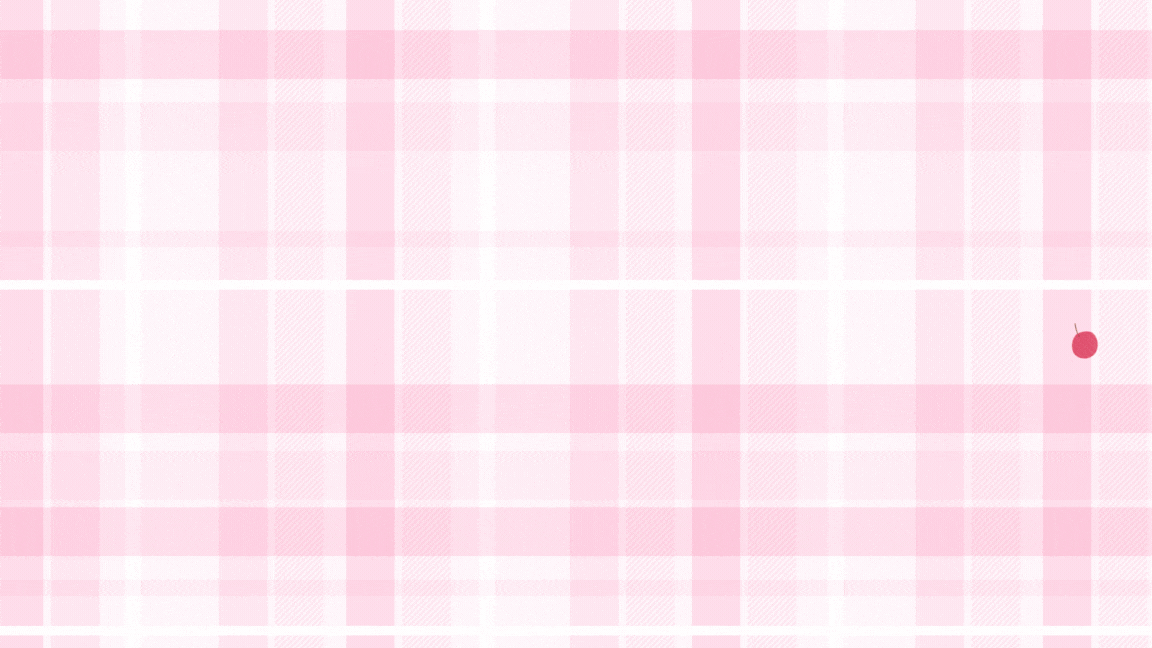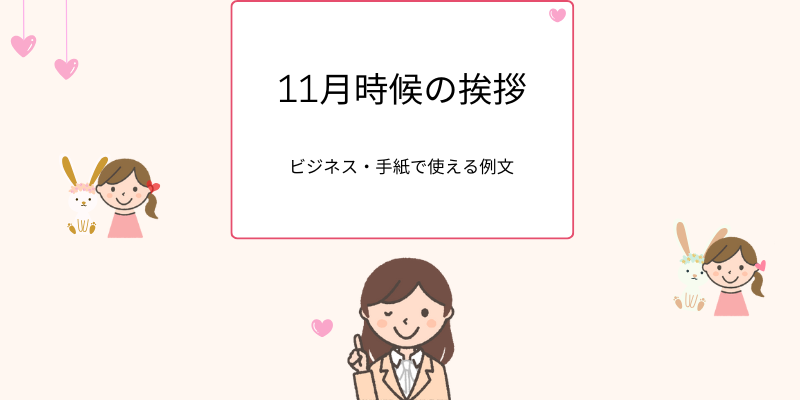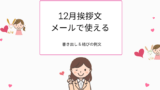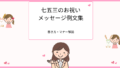11月は、紅葉が深まり、冬の気配を感じ始める美しい季節です。ビジネスメールや手紙では、「向寒の候」「立冬の候」「初霜の候」など、秋から冬へ移ろう時期にふさわしい時候の挨拶がよく使われます。この記事では、11月上旬・中旬・下旬の時候の挨拶一覧とともに、ビジネスで使える例文や季語の意味をわかりやすく紹介します。相手に季節感と丁寧な印象を伝える文面づくりの参考にしてください。
11月の時候の挨拶とは?季語と使い方の基本
11月の時候の挨拶は、秋から冬への季節の変わり目を表す言葉が多く使われます。紅葉や初霜など自然の情景を取り入れると、季節感が伝わりやすくなります。ビジネスメールや手紙では、「○○の候」「○○のみぎり」「○○の折」を使うのが一般的です。
「○○の候」「○○のみぎり」「○○の折」とは?
→手紙やビジネス文書の冒頭で使われる「時候の挨拶」の定型句で、季節や時期を表す言葉の後に付けて「○○という季節・時期ですので」という意味を表します。

・立冬のみぎり、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
・秋晴れの候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
11月時候の挨拶一覧
11月上旬・中旬・下旬に使いやすい挨拶文の例をまとめています。メールや手紙で季節感を伝える際にご活用ください。
| 時候の挨拶 | 意味 | 使用時期の目安 |
| 清秋の候 (せいしゅうのこう) | 空が澄みわたり、清々しい秋を感じる時期のご挨拶。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 紅葉の候 (こうようのこう) | 山や街路樹が色づき始める頃のご挨拶。紅葉狩りの話題にもつながり、プライベートの便りにおすすめです。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 晩秋の候 (ばんしゅうのこう) | 秋が終わりを告げ、冬の気配が感じられる時期のご挨拶。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 錦秋の候 (きんしゅうのこう) | 山々が美しく染まる時期のご挨拶。鮮やかな紅葉をイメージさせる華やかな表現です。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 霜降の候 (そうこうのこう) | 10月下旬、霜が降りる頃のご挨拶。晩秋の冷え込みを伝え、体調を気づかう文面にぴったりです。 | 10月23日〜11月7日頃 |
| 深秋の候 (しんしゅうのこう) | 秋も深まり、冬の訪れを感じる時期のご挨拶。季節の移ろいを伝える、落ち着いた表現です。 | 10月下旬〜11月7日頃 |
| 夜寒の候 (よさむのこう) | 秋が深まり、特に夜間の冷え込みが強く感じられる頃のご挨拶。相手の体調を気遣う文面に優しく寄り添う表現です。 | 11月上旬〜12月10日頃 |
| 初冬の候 (しょとうのこう) | 暦の上で冬に入り、冬の始まり(孟冬)を感じる時期のご挨拶。 | 11月7日〜12月7日頃 |
| 向寒の候 (こうかんのこう) | 寒さが厳しくなる時期へ向かう途中のご挨拶。相手の健康管理を丁寧に促す文面に幅広く使える汎用性の高い表現です。 | 11月7日〜12月20日冬至 |
| 深冷の候 (しんれいのこう) | 寒さが一段と深まった時期のご挨拶。厳しい寒さを表現し、フォーマルなビジネス文書や、より丁寧に使いたい時に。 | 11月中 |
| 落葉の候 (らくようのこう) | 秋の終わりと冬の静けさが感じられる情景を表現し、落ち着いた季節の移ろいを伝えたい時に適しています。 | 11月中旬〜11月中 |
| 小雪の候 (しょうせつのこう) | 雪が降らない地域でも、寒さが深まり、冬の始まりを実感する時期の挨拶として使えます。 | 11月21日〜12月7日頃 |
ビジネスメールで使える11月の挨拶文の書き方ポイント
時候の挨拶は、主に「前文」と呼ばれる書き出しの部分を構成します。一般的な流れは以下の通りです。
- 頭語(拝啓など)
- 時候の挨拶(「向寒の候」など)
- 相手の健康や繁栄を気遣う言葉(安否・繁栄の言葉)or感謝の言葉(平素の感謝)
- 本題へ

↓季語が思いつかない時には?(季語を使わない(口語調)挨拶の紹介)
時候の挨拶に漢語調の季語が思いつかない、または少しカジュアルに伝えたい場合は、情景を表す自然な言葉で問題ありません。
例1:(寒さを表現) 朝晩の冷え込みが厳しくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
例2:(紅葉を表現) 秋も深まり、紅葉が見頃を迎えています。 平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
11月上旬の時候の挨拶と例文(書き出し・結び)
11月上旬は、紅葉が色づき秋の深まりを感じる頃。季語には「紅葉」「霜月」「錦秋」「深秋」などがあります。ビジネスメールでは「紅葉の候」などの時候の挨拶から入り、相手の健康や繁栄を気遣う言葉を添えるのが基本です。結びには「今後ますますのご発展をお祈り申し上げます」などを入れると丁寧な印象になります。
季語:「紅葉」「霜月」「錦秋」「深秋」「暮秋」
時期の目安:10月下旬〜立冬(7日頃)の前日まで。まだ秋の終わりの色が濃い時期。

【ビジネスメール例文】
・紅葉の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。今後とも変わらぬお引き立てのほどお願い申し上げます。
・錦秋の折、皆さまにおかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じます。益々のご活躍をお祈り申し上げます。
【カジュアル・プライベート向け例文】
・紅葉が美しく色づく季節となりましたね。お元気にお過ごしでしょうか。実りの秋、どうぞ健やかにお過ごしください。
・朝晩の冷え込みが増してきました。どうぞお体を大切にお過ごしください。またお会いできる日を楽しみにしております。

11月中旬の時候の挨拶と例文(書き出し・結び)
11月中旬は「立冬」や「初霜」など、暦の上で冬を迎える時期です。季語には「立冬」「初霜」「冬支度」「向寒」などがあり、寒さを意識した表現が中心になります。ビジネスメールでは「向寒のみぎり」などの挨拶に続き、「ご健康をお祈り申し上げます」と結ぶと好印象です。手紙では「寒さ厳しき折、どうぞお体を大切に」と添えるのもおすすめです。
季語:「立冬」「初霜」「冬支度」「向寒」「小春日和」
時期の目安:立冬(7日頃)〜小雪(22日頃)の前日まで。暦の上では冬の始まり。

【ビジネスメール例文】
・向寒のみぎり、皆さまのご健康をお祈り申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。
・立冬の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。引き続きご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
【カジュアル・プライベート向け例文】
・暖房が恋しい頃となりましたね。お変わりありませんか。寒さが増す季節、どうぞ温かくしてお過ごしください。
・朝の冷え込みに冬の訪れを感じる季節になりました。風邪など召されませんように。また近況をお聞かせくださいね。
11月下旬の時候の挨拶と例文(書き出し・結び)
11月下旬は「小雪」や「霜寒」「初冬」などの季語が使われる時期。冬の足音が近づくこの季節は、ビジネスメールでも「小雪の候」「初冬の折」などの丁寧な表現が適しています。結びには「年末に向けてご多忙のことと存じますが、ご自愛ください」など、相手を思いやる一文を添えると印象が良くなります。
季語:「小雪」「初冬」「霜寒」「木枯らし」
時期の目安:小雪(22日頃)〜月末。本格的な冬の気配が色濃くなる時期。

【ビジネスメール例文】
・小雪の候、貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
・霜寒の折、皆様におかれましてはご健勝のことと拝察いたします。年末に向けて何かとご多忙のことと存じますが、どうぞご自愛ください。
・初冬の折、皆さまにおかれましてはお健やかにお過ごしのことと拝察いたします。来月も変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
【カジュアル・プライベート向け例文】
・木枯らしが吹き始め、冬の訪れを感じる今日この頃です。どうぞお体を大切にお過ごしください。
・小春日和のうららかな日差しが続く頃となりました。お風邪など召されませぬよう、どうぞご自愛ください。
・冬の訪れを感じるこの頃、どうぞお体を冷やさぬようお気をつけください。温かいお鍋が恋しい季節ですね。近いうちにお会いできれば嬉しいです。
・日脚(ひあし)がめっきり短くなり、ひだまりの恋しい季節となりましたね。お元気にお過ごしでしょうか。年の瀬が近づきますが、どうぞお体を大切にお過ごしください。
まとめ
11月の時候の挨拶は、「紅葉の深まり」から「冬の訪れ」へと移ろう季節の情景を伝える大切な挨拶です。特にビジネスシーンでは、「○○の候」「○○のみぎり」「○○の折」などの漢語調の挨拶を添えることで、より丁寧で信頼感のある文面になります。
一方で、もう少し柔らかく親しみを込めたい場合は、「朝晩の冷え込みが厳しくなりました」「紅葉が見頃を迎えています」など、自然な口語調でも十分に季節感を伝えられます。この記事が、あなたの心遣いが伝わる11月のビジネスコミュニケーションの一助となれば幸いです。今年の晩秋も、どうぞ健やかにお過ごしください。