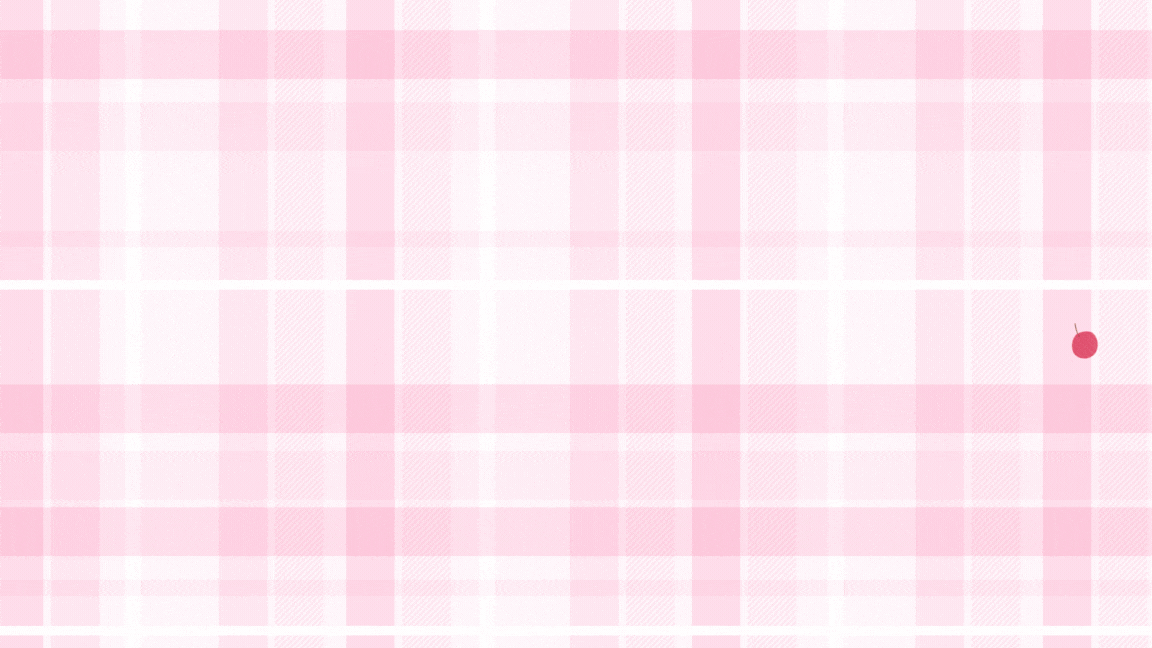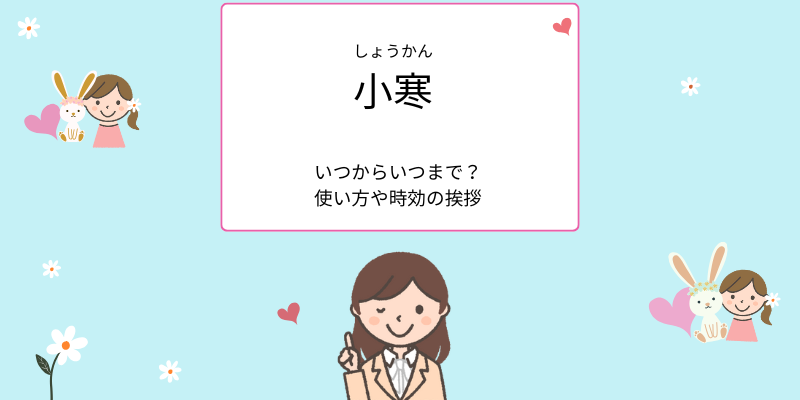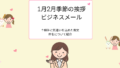「小寒(しょうかん)」という言葉を聞いたことはありますか?小寒は二十四節気(にじゅうしせっき)の一つで、本格的な寒さが始まる頃を意味します。この記事では、小寒はいつからいつまでなのか、その意味や由来、この時期にすること、そして時候の挨拶まで、詳しく解説します。小寒の時期ならではの冬の暮らしをより豊かに彩りましょう。手紙やビジネスメールで使える時候の挨拶もご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
小寒(しょうかん)とは?意味と由来
小寒とは二十四節気(太陽の動きをもとに1年を24に分けた、季節を表す区分です。)の一つで、本格的な寒さが始まる直前の時期を指します。

「小寒」という名前だけど、寒さの入り口なんですね♡
小寒の意味
「小寒」は、「寒さがまだ小さい」という意味を持っていますが、実際にはこれから寒さが厳しくなる時期の入り口です。一年で最も寒い時期とされる「大寒(だいかん)」に向かう前の段階で、寒さが徐々に増していく時期を表しています。そのため、「小寒」は「寒の入り(かんのいり)」とも呼ばれます。
小寒と大寒の関係性:小寒は寒さの始まり、大寒は寒さのピークになります。
小寒はいつからいつまで?2025年の日付
2025年の小寒は、1月5日(日) です。先ほどもお伝えしましたが、これは「寒の入り」とも呼ばれ、小寒の期間が始まる日を指します。
小寒の期間
小寒は、毎年1月5日ごろから1月19日ごろまでの約15日間を指します。太陽の動きに基づいて定められる二十四節気は、年によって日付が1日程度前後します。
【補足です】
国立天文台の資料によれば、2025年の小寒は以下の通りです。
小寒(寒の入り): 2025年1月5日(日)午前11時33分
この時刻をもって、小寒の期間が始まります。

「冬至」「大寒」と比較するとわかりやすいです♡
冬至(とうじ):太陽が最も南に位置する日で、一年で昼が最も短い日です。小寒の約15日前です。
大寒(だいかん):一年で最も寒い時期とされる日で、小寒の約15日後です。
小寒の時候の挨拶:メールや手紙で使える例文
小寒は本格的な寒さの始まりを告げる時期ですので、相手の健康を気遣う言葉や、寒さに関する言葉を入れることをおすすめします。ここでは、ビジネスシーンや日常で使えるメールや手紙で使える例文を紹介します。

↓時候の挨拶の書き方の基本です♡
| 1頭語 | 手紙の冒頭に書く言葉(例:拝啓、謹啓) |
| 2時候の挨拶 | 季節を表す言葉や、相手の安否を気遣う言葉 |
| 3本文 | 伝えたい内容 |
| 4結びの言葉 | 手紙の末尾に書く言葉(例:敬具、敬白) |
| 5後付 | 日付、署名など |
【時候の挨拶で使える言葉】
時候の挨拶は、本文の前置きとして使用します。、簡潔にまとめて使いましょう。
・小寒の候:最も一般的な表現で、改まった手紙やビジネス文書に適しています。
例文:小寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
・寒の入り:小寒に入る時期を表す言葉で、やや口語的な表現になります。親しい人への手紙やメールに適しています。
例文:寒の入りを迎え、一段と寒くなってまいりました。お変わりありませんか。
・寒さ厳しき折:寒さが厳しい状況を表す表現で、相手の体調を気遣う言葉と組み合わせて使われることが多いです。
例文:寒さ厳しき折、皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。
・寒風が身に染みるころ:寒さの様子を具体的に表現した言葉で、情景が目に浮かぶような表現です。
例文:寒風が身に染みるころとなりましたが、お変わりございませんか。
・寒さ厳しくなってまいりましたが:現在の状況を伝えるとともに、相手への気遣いを表す表現です。
例文:寒さ厳しくなってまいりましたが、風邪などひかれていませんでしょうか。
【ビジネスシーンで目上の人、取引先などに使う場合】

↓メールの書き方です♡
1)件名:小寒のご挨拶
〇〇様
小寒を迎え、一段と寒さが厳しくなってまいりました。 皆様いかがお過ごしでしょうか。
(本文)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2)件名:小寒のご挨拶
〇〇様
小寒を過ぎ、いよいよ寒さも本番となりましたが、お変わりありませんか。
こちらはつつがなく過ごしております。
(本文)

↓手紙の書き方です♡
1)拝啓
小寒の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
(本文)
敬具
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2)謹啓
寒さ厳しき折、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。
(本文)
敬白
小寒の時期にすること・過ごし方
小寒は本格的な寒さの始まりであり、体調管理に気を配りながら、冬ならではの過ごし方を楽しみましょう。
七草粥(ななくさがゆ):1月7日に、春の七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)を入れて炊いた粥を食べる習慣があります。お正月のご馳走で疲れた胃腸を休め、無病息災を祈る意味があります。
寒中見舞い:小寒から節分までの「寒の内」に出すあいさつ状です。年賀状を出しそびれた場合や、喪中の方へのごあいさつなどに用いられます。

小寒は寒さが厳しくなる時期ですが、春の訪れも少しずつ近づいています。体調に気を付けてお過ごしください♡
まとめ
小寒(しょうかん)は二十四節気の一つで、本格的な寒さを迎える時期です。古くから日本の生活や文化に深く根付いており、季節の移り変わりを感じる上で重要な節目となっています。小寒の時期は、寒さが厳しく体調を崩しやすい時期でもあります。昔からの知恵を活かし、寒さ対策をしっかりと行い、体を温めることを意識した生活を送ることで、元気に冬を乗り切ることが大切です。