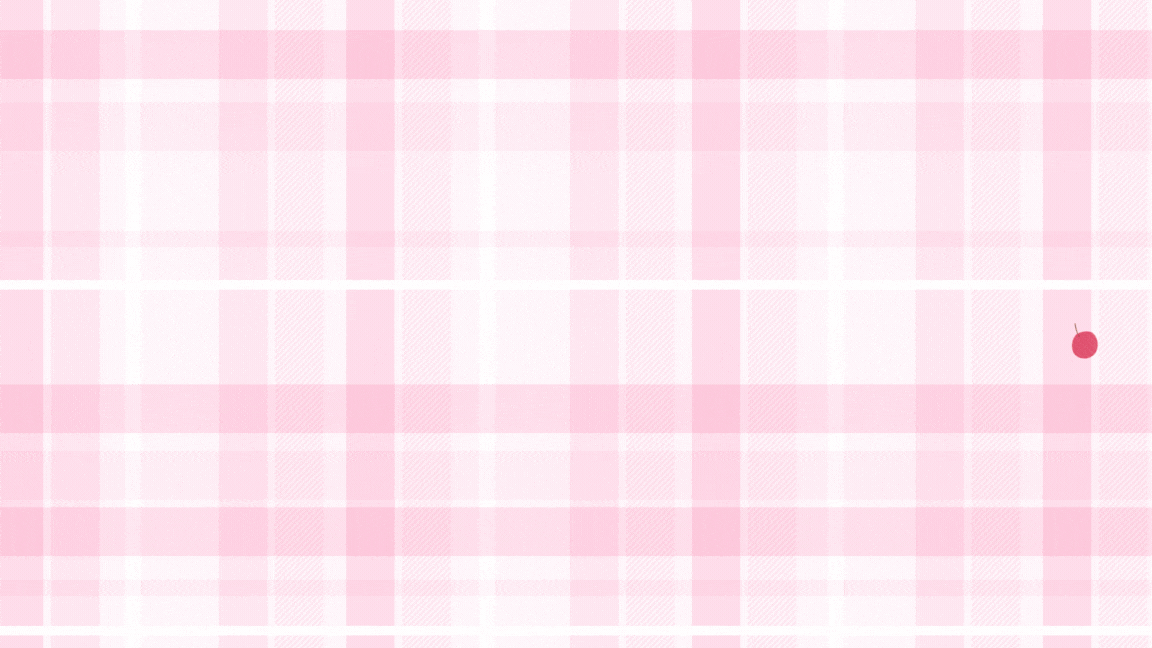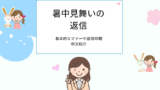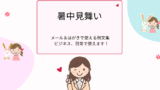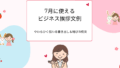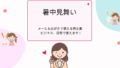本格的な夏が到来し、暑さが厳しくなる頃に送り合う「暑中見舞い」。日頃お世話になっている方への感謝や、なかなか会えない方への近況報告を兼ねて送る日本ならではの風習です。でも、「いつからいつまでに出せばいいの?」「どんなマナーがあるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、暑中見舞いの意味や送る時期、書き方のマナーまで、初めての方にも分かりやすく解説します。今年の夏は、心を込めた暑中見舞いで大切な人へ涼を届けてみませんか。
暑中見舞いはいつからいつまで?送る時期の基本

暑中見舞いを送る時期についてルールがあります。一般的には「夏の土用の期間」から「立秋の前日まで」とされています。具体的な日付で言うと、以下のようになります。
暑中見舞いを送る期間

↓「暑中見舞い」を送る期間です♡
小暑(7月7日頃)から立秋(8月7日頃)の前日まで
この期間は、一年で最も暑い時期にあたり、相手の健康を気遣う気持ちを伝えるのに適しています。ただし、地域によっては梅雨明けが遅かったり、夏の暑さのピークがずれたりすることもあります。そのため、相手が住む地域の気候なども考慮して送るのが、心遣いのポイントです。
時期を過ぎてしまったら「残暑見舞い」に
もし、立秋を過ぎてしまった場合は、「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」として送るのがマナーです。残暑見舞いは、立秋から8月末頃までに送るのが一般的です。
残暑見舞いの期間:立秋(8月7日頃)から8月末日まで
時期を間違えて送ってしまうと、相手に失礼にあたる可能性もあるため、注意しましょう。
暑中見舞いの意味とは?日本の伝統的な風習
暑中見舞いは、日本の夏の伝統的な風習です。簡単に言うと、夏の最も暑い時期に、なかなか会えない方や、お世話になった方の健康を気遣い、「元気でお過ごしですか?」と相手を思いやって送る季節のご挨拶です。

↓「暑中見舞い」の起源について少し詳しく♡
この習慣は、江戸時代にさかのぼります。お盆の時期に故郷へ帰省する際、先祖の霊へお供え物を持参する習慣が始まりとされています。それが時代とともに変化し、お世話になった方へ贈り物や手紙を贈って、お互いの安否を尋ねるようになりました。明治時代に郵便制度が整備されてからは、現在のようにハガキや手紙で送ることが一般的になりました。
【現代における暑中見舞いの役割】現代では、次のような目的で送られることが多いです。
- なかなか会えない方への近況報告
- 日頃お世話になっている方への感謝
- 家族や友人、知人の健康を気遣う気持ち
- ビジネスシーンでの顧客や取引先への挨拶
厳しい暑さの中で、相手の健康を気遣い、心ばかりの涼を届ける日本の美しい文化と言えるでしょう。
暑中見舞いを送る際のマナーとポイント
暑中見舞いは、相手への配慮が大切です。はがきで送る場合とメールで送る場合、それぞれに押さえておきたいマナーがあります。
はがきで送る場合のマナー
暑中見舞いは、年賀状と同様に季節の挨拶状ですので、「拝啓」「敬具」などの頭語・結語は不要です。句読点も打たないのが一般的です。

もし読点をいれたいなと思ったら、代わりにスペースを設けたり、改行したり工夫をしてみる♡
・お見舞いの言葉:「暑中お見舞い申し上げます」と、他の文字よりも大きめに書きます。
・縦書きと横書き: 特に決まりはありませんが、目上の人には縦書きがよりフォーマルな印象になります。
・喪中の場合: 暑中見舞いは「お見舞い」であり「お祝い」ではないため、喪中でも送っても問題ないとされています。ただし、相手の心情を考慮し、派手な絵柄や文面は避け、簡潔な内容にしましょう。特に、四十九日以内など直近の場合は、控えるのが無難です。
メールで送る場合のマナー
メールで暑中見舞いを送る場合も、基本的な時期(小暑〜立秋の前日)ははがきと同様です。ただし、メールは手軽な分、より相手への配慮が求められます。
・送る時間帯に配慮する:仕事関係の相手には、業務時間内に送るのが一般的です。早朝や深夜など、相手の迷惑になる時間帯は避けましょう。
・件名を分かりやすくする:「暑中お見舞い申し上げます」や「〇〇(自分の名前)より暑中お見舞い」など、具体的に記載しましょう。
・「拝啓」「敬具」などの頭語・結語は不要です。
・句読点はメールでは通常通り使用します。
暑中見舞いの基本的な構成
暑中見舞いは、はがきでもメールでも、おおよそ決まった構成で書くのが一般的です。夏の挨拶状として、相手への気遣いや感謝を伝える大切な手段ですので、ポイントを押さえて気持ちを届けましょう。
1)書き出しの挨拶(主文)
「暑中お見舞い申し上げます」
2)季節の挨拶・相手の安否を気遣う言葉
季節を表す言葉や、相手の健康を気遣う言葉を綴ります。

「連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。」
「梅雨明けとなり、いよいよ本格的な夏を迎えます。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。」
3)自分の近況報告や感謝の言葉
簡潔に近況を報告したり、日頃の感謝を伝えたりします。

「おかげさまで、私ども家族一同元気に過ごしております。先日、〇〇へ旅行し、楽しい夏の思い出ができました。」
「日頃は大変お世話になっております。先日は素敵なお品をお贈りいただき、誠にありがとうございました。」
「おかげさまで、仕事も順調に進んでおります。これもひとえに皆様のご支援の賜物と感謝申し上げます。」
4)相手の健康や活躍を願う結びの言葉
相手の健康や今後の繁栄を祈る言葉で締めくくります。

「酷暑厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。」
「時節柄、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。」
「今後一層の暑さが予想されますので、どうかくれぐれもご無理なさらないでください。」
5)日付
「令和〇年 盛夏」などと記します。残暑見舞いの場合は「令和〇年 立秋」とします。
まとめ
暑中見舞いは、夏の暑さが厳しい時期に相手の健康を気づかう、日本の伝統的なご挨拶です。ビジネスでもプライベートでも、日頃の感謝や思いやりの気持ちを伝えるきっかけになります。送る時期やマナーを守れば、はがきでもメールでも、心のこもった暑中見舞いはしっかり相手に届きます。
今年の夏は、形式にとらわれすぎず、大切な人やお世話になった方へ、涼やかなご挨拶を届けてみませんか?