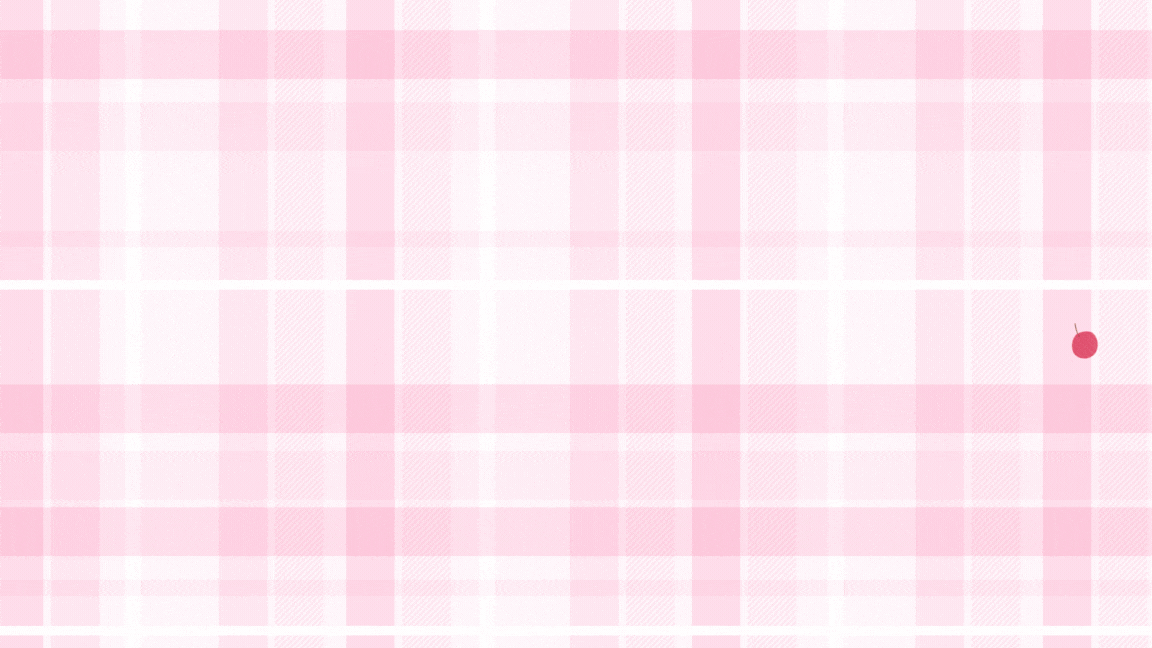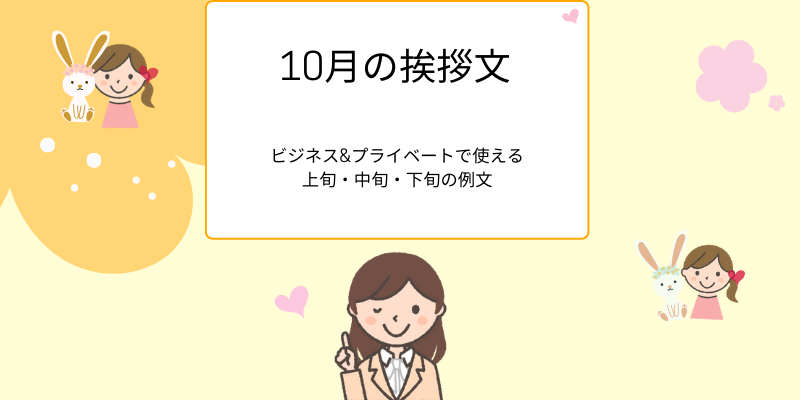11月は秋が深まり、紅葉や初霜など季節の移ろいを感じる時期です。本記事では、11月上旬・中旬・下旬に使える挨拶文を、ビジネス・プライベートの両シーンで紹介します。メールや手紙、SNSで季節感を伝える際に役立つ文例を豊富に掲載し、七五三や勤労感謝の日、旬の食べ物など、季節ならではの話題を添えるポイントも解説します。向寒の折にふさわしい体調を気づかう表現や、温かみのある文章の工夫まで、幅広く参考にしていただけます。
11月時候の挨拶一覧
11月は晩秋から初冬へと移ろう季節で、日ごとに寒さが深まる中に小春日和の穏やかさが感じられます。「立冬」「霜月」「向寒」「落葉の候」「錦秋の候」など、季節を感じる言葉を挨拶に取り入れると、相手と季節の移ろいを共有しやすくなります。
ビジネスでは、体調への気遣いや年末に向けたねぎらいの言葉を添えると丁寧な印象に。プライベートでは、紅葉や冬支度の話題を加えると親しみやすい文面になります。
以下では、11月上旬・中旬・下旬に使いやすい挨拶文の例をまとめています。メールや手紙で季節感を伝える際にご活用ください。
| 時候の挨拶 | 意味 | 使用時期の目安 |
| 清秋の候 (せいしゅうのこう) | 空が澄みわたり、清々しい秋を感じる時期のご挨拶。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 紅葉の候 (こうようのこう) | 山や街路樹が色づき始める頃のご挨拶。紅葉狩りの話題にもつながり、プライベートの便りにおすすめです。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 晩秋の候 (ばんしゅうのこう) | 秋が終わりを告げ、冬の気配が感じられる時期のご挨拶。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 錦秋の候 (きんしゅうのこう) | 山々が美しく染まる時期のご挨拶。鮮やかな紅葉をイメージさせる華やかな表現です。 | 10月8日〜11月7日頃 |
| 霜降の候 (そうこうのこう) | 10月下旬、霜が降りる頃のご挨拶。晩秋の冷え込みを伝え、体調を気づかう文面にぴったりです。 | 10月23日〜11月7日頃 |
| 深秋の候 (しんしゅうのこう) | 秋も深まり、冬の訪れを感じる時期のご挨拶。季節の移ろいを伝える、落ち着いた表現です。 | 10月下旬〜11月7日頃 |
| 夜寒の候 (よさむのこう) | 秋が深まり、特に夜間の冷え込みが強く感じられる頃のご挨拶。相手の体調を気遣う文面に優しく寄り添う表現です。 | 11月上旬〜12月10日頃 |
| 初冬の候 (しょとうのこう) | 暦の上で冬に入り、冬の始まり(孟冬)を感じる時期のご挨拶。 | 11月7日〜12月7日頃 |
| 向寒の候 (こうかんのこう) | 寒さが厳しくなる時期へ向かう途中のご挨拶。相手の健康管理を丁寧に促す文面に幅広く使える汎用性の高い表現です。 | 11月7日〜12月20日冬至 |
| 深冷の候 (しんれいのこう) | 寒さが一段と深まった時期のご挨拶。厳しい寒さを表現し、フォーマルなビジネス文書や、より丁寧に使いたい時に。 | 11月中 |
| 落葉の候 (らくようのこう) | 秋の終わりと冬の静けさが感じられる情景を表現し、落ち着いた季節の移ろいを伝えたい時に適しています。 | 11月中旬〜11月中 |
| 小雪の候 (しょうせつのこう) | 雪が降らない地域でも、寒さが深まり、冬の始まりを実感する時期の挨拶として使えます。 | 11月21日〜12月7日頃 |
11月上旬に使える挨拶文
11月上旬は、暦の上では立冬を迎え、晩秋から初冬への移ろいを感じる時期です。この時期の挨拶文では、「秋の名残」と「初冬への配慮」を織り交ぜることが大切です。
時候の挨拶:「晩秋の候」「錦秋の候」(秋の終わりを強調したい場合) 「立冬の候」「向寒の候」(暦や寒さの始まりを強調したい場合) 特に7日頃の立冬を境に使い分けると丁寧です。
季節の話題:紅葉、七五三、木枯らし、初霜、山茶花や菊、鍋物など冬支度の話題。「読書の秋」「芸術の秋」の締めくくり表現もおすすめです。
気遣いの言葉:「向寒の折、どうぞご自愛ください」「日毎に寒さがつのる時節柄、お体大切にお過ごしください」→ 本格的な冬に向けての健康配慮を添えると、ビジネスでもプライベートでも丁寧な印象になります。


「晩秋」から「初冬」へと季節が移り変わる時期であり、朝晩の冷え込みが厳しくなり、本格的な冬支度が始まる頃です♡
ビジネス向け例文
ビジネスシーンでは、11月特有の「秋の終わり」と「冬の始まり」を感じさせる言葉で、相手の健康や業務への労いを伝えることが大切です。ここでは、フォーマルな漢語調から、社内や親しい取引先に適した口語調、プライベートで心温まる例文まで、11月に使える挨拶文例をご紹介します。
書き出しの例文【漢語調:フォーマル】
ビジネス文書や目上の人に送る場合に適した、格式のある挨拶表現です。

「向寒の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
解説:寒さに向かう時期を意味する11月全般にふさわしい表現です。取引先や目上の方へ使える、最も一般的で格式ある書き出しです。
「立冬の候、皆様にはますますご健勝のことと拝察いたします。」
解説:11月上旬(7日頃から)にふさわしい、暦の上での冬の始まりを表す時候の挨拶です。落ち着いた印象になります。
「暮秋の折、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
解説:「暮秋」は秋の終わりを意味します。ゆく秋を惜しみつつ、相手の発展を願う気持ちを伝える丁寧な書き出しです。(11月上旬~中旬目安)
結びの例文【漢語調:フォーマル】
11月の季節感にふさわしい、体調への配慮とねぎらいを込めた結びの例文です。

「向寒の折、くれぐれもご自愛くださいますようお願い申し上げます。」
解説:寒さが増す時期に、相手の健康を強く願う丁寧な結びの言葉です。
「初冬に向かう時節柄、貴社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。」
解説:冬の訪れを意識させつつ、相手のビジネスの成功を祈る、前向きな結びの言葉です。
「日増しに秋が深まる折、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」
解説:秋の深まりを踏まえ、体調への配慮と相手の幸せを願う丁寧な結びの言葉です。
「冷え込みが厳しくなる折、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」
解説:1月上旬の冷え込みを踏まえ、体調を気遣う穏やかな結びです。
「深まる秋の実りが、さらなるご発展をもたらしますようお祈り申し上げます。」
解説:「実り」や「発展」を重ねることで、ビジネス相手へのエールを込めた前向きな表現になります。
書き出しの例文【口語調:カジュアル】

親しい人や日頃の感謝を伝える際に使える例文です♡
「木々の色づきが一段と美しくなってまいりましたが、皆様お元気でいらっしゃいますか。」
解説:紅葉を取り入れることで、季節の情緒を感じさせる温かみのある書き出しです。
「朝晩はぐっと冷え込むようになりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:11月上旬の寒暖差を踏まえた、柔らかく自然な挨拶です。
「穏やかな小春日和が続いておりますが、お健やかにご活躍のことと存じます。」
解説:11月ならではの暖かく穏やかな晴れの日(小春日和)を話題に取り入れ、安否を問う書き出しです。

暦の上では冬となりましたが、小春日和の穏やかな日も見られ、寒さの兆しと時折の暖かさが入り混じる時期です♡
結びの例文【口語調:カジュアル】
「紅葉が見頃を迎える季節、実りある毎日をお過ごしください。」
解説:季節の話題を入れることで、親しみやすい印象の結びの言葉です。
「これから本格的な寒さに向かいますので、どうぞお体を大切にお過ごしください。」
解説:「本格的な寒さ」を意識させ、季節の変わり目の注意を促す、親切な結びの言葉です。

↓書き出し部分から本文へのつなぎ(例)も参考にしてください♡
・「向寒の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、〜」
解説:11月の季語「向寒の候」を用いて、時候の挨拶を述べた後、本題に入ります。丁寧なビジネス文書の書き出しとして最適です。
・「木枯らしが吹き、冬の訪れを感じる季節となりましたが、貴社にはいよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。早速ですが、〜」
解説:より季節感を出すなら、「木枯らし」といった季節の言葉を入れることで親しみやすく丁寧な印象になります。
・「日頃は格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。朝晩の冷え込みが身に染みる季節となりましたが、〜」
解説:時候の挨拶を省略し、日頃の感謝を伝えた後、口語調の体調気遣いを添えて本題に入る、簡潔で共感的な書き出しです。
プライベート向け例文
11月上旬は、秋が深まり、街には金木犀の香りや紅葉の色づきが広がる美しい季節。プライベートな手紙やLINE、メッセージなどで季節の話題を添えると、温かみのある印象になります。
書き出しの例文
「色鮮やかな紅葉が、山々を彩る頃となりました。お変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:紅葉の見頃を話題に取り入れ、日本の美しい季節感を共有する柔らかな挨拶です。
「金木犀の香りが名残惜しい季節になりました。お変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:季節の終わりを感じさせる表現で、情緒的な書き出しです。
「こたつや暖房器具が恋しくなる季節となりましたね。お風邪など召されていませんか。」
解説:冬支度の話題を入れることで、親近感を抱かせ、相手の健康を気遣う温かい書き出しです。
結びの例文
「冬の気配が濃くなってまいりましたが、穏やかな小春日和をどうぞお健やかにお楽しみください。」
解説:冬の訪れと小春日和という対比の言葉で、この時期の情緒を表現し、相手の穏やかな日々を願います。
「秋の夜長を、どうぞゆったりとお過ごしください。」
解説:秋の静けさを伝え、穏やかな気持ちを込めた結びです。
「冬の足音が近づいています。どうぞお体を温かくしてお過ごしくださいね。」
解説:11月らしい冷え込みを意識した、優しい締めくくり方です。

↓以下のテンプレートは、親しい間柄に使ってみてください♡
〇〇様、ご無沙汰しております。
日ごとに秋が深まり、鮮やかな紅葉の季節となりました。暦の上では冬を迎えましたが、〇〇様におかれましては、お変わりなくご活躍のことと存じます。
朝晩の冷え込みが身に染みる頃ですので、どうぞご無理なさらず、お体を大切にお過ごしください。
〇〇様
落ち葉が風に舞う季節となり、今年も残り少なくなってまいりました。お元気でいらっしゃいますか。
小春日和の穏やかな日もありますが、どうぞ体調を崩されないようご自愛ください。実り豊かな秋のひとときを、存分にお楽しみくださいね。
11月中旬に使える挨拶文
11月中旬は、暦の上で「立冬」を過ぎ、本格的な冬の足音が聞こえ始める時期です。紅葉は終盤を迎え、木枯らしが吹き、朝晩の冷え込みが厳しくなります。この時期の挨拶文は、「秋の名残を惜しむ風情」「寒さへの気遣い」がポイントです。ビジネスでは「初冬の候」や「向寒の候」が適しています。
時候の挨拶:「向寒の候」「夜寒の候」寒さを意識する表現、「初冬の候」冬の始まりを感じさせます。
季節の話題:紅葉の終盤、落ち葉、木枯らし、初霜、七五三、温かい鍋物や温泉が恋しいといった冬支度、空気が澄んで星が綺麗といった話題。
気遣いの言葉:本格的な寒さや乾燥への体調管理、インフルエンザなど感染症予防を促す言葉が効果的です。「冬の寒さ厳しき折」「ご自愛専一に」など、丁寧な言葉で心遣いを伝えます。

ビジネス向け例文
ビジネスシーンでは、11月中旬の時期にふさわしい時候の挨拶を使いながら、寒さへの配慮と日頃の感謝を丁寧に伝えることが大切です。
書き出しの例文【漢語調:フォーマル】
ビジネス文書や目上の人に送る場合に適した、格式のある挨拶表現です。

「向寒の候、貴社におかれましては、いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。」
解説:寒さに向かうこの時期に、今後の発展を強く願う気持ちを込めた、非常に丁寧な表現です。
「初冬の候、皆様には一段とご健勝のことと拝察いたします。」
解説:暦の上での冬(立冬以降)に入ったことを示す「初冬」を使った書き出し。落ち着いた印象になります。
「落葉の候、貴社におかれましてはますますのご発展をお祈り申し上げます。」
解説:木々が葉を落とし始める11月中旬を表す「落葉の候」を使い、相手への祈りを込めています。
結びの例文【漢語調:フォーマル】

「落葉深まる季節、貴社のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。」
解説:落葉の進む秋を季節感として入れつつ、健康と事業の発展を願う結びです。
「深冷の折、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。」
解説:朝晩の冷え込みが増すこの時期に、相手の体調を気遣う気持ちを込めた結びの言葉です。
「暮秋のみぎり、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。」
解説:秋の季節感を伝えつつ、未来の繁栄を願うフォーマルな結びです。

「〇〇の候」は「〇〇のみぎり」や「〇〇の折」に置き換えて使うことができます。基本的に「この時期に」「この時に」という共通の意味合いを持っています。
書き出しの例文【口語調:カジュアル】
親しい間柄や社内メールでは、季節の情景や温かみのある言葉を選びましょう。

「日ごとに寒さが深まり、温かいものが恋しくなる時節となりました。お元気でいらっしゃいますか。」
解説:日常生活の情景を話題にし、親しみやすく、体調への配慮を込めた書き出しです。
「冷たい木枯らしが身に染みる季節となりましたが、皆様にはますますご活躍のことと存じます。」
解説:木枯らしという季語を取り入れつつ、相手の活躍を願う前向きな書き出しです。
「暦は立冬を過ぎ、冬の気配を感じる今日この頃ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:季節の移り変わりを話題にした自然な挨拶文。親しみを込めて相手の近況を尋ねます。
結びの例文【口語調:カジュアル】

「朝晩の冷え込みも増してまいりましたので、どうぞご体調を崩されませんようご自愛ください。」
解説:健康を第一に気遣う表現。メール文末に添えやすく、温かい心遣いが伝わります。
「小春日和の穏やかな日々、充実した季節をお過ごしください。」
解説:時折訪れる穏やかな天候(小春日和)に触れ、優しく結ぶことで、親近感のある印象になります。
「本格的な寒さに向かう折、引き続きご健勝にてお過ごしになられますようお祈りいたします。」
解説:これからの寒さに備える気持ちを込めた、丁寧な結びの言葉です。
プライベート向け例文
個人的な手紙やメッセージでは、この時期ならではの美しい情景や、相手の生活に寄り添う温かい言葉を選ぶと良いでしょう。
書き出しの例文

「冷たい風に舞う落ち葉に、秋の終わりを感じる今日この頃ですが、お変わりありませんか。」
解説:秋から冬への移ろいを具体的に表現することで、共感を生み、相手の近況を優しく尋ねる書き出しです。
「山茶花(さざんか)の鮮やかな色が、冬の寒さを忘れさせてくれる季節となりましたね。お元気で過ごされていますか。」
解説:11月を彩る花(山茶花)を取り入れることで、季節感のある書き出しになります。
「小春日和のうららかな陽射しが心地よい季節ですが、〇〇さんはお忙しくされていないでしょうか。」
解説:穏やかな天候に触れ、季節感と親しみを込めて相手の様子を伺う、柔らかな書き出しです。
結びの例文

「実りの秋を楽しみながら、元気にお過ごしください。」
解説:秋の季節感を込めつつ、前向きな印象で締めくくります。
「秋晴れの空の下、〇〇さんにとって素敵な毎日になりますように。」
解説:10月らしいポジティブな言葉で、相手の幸せを願う、爽やかで前向きな結びの言葉です。
「急に冷え込んできましたので、どうぞご体調を崩されないようご自愛ください。」
解説:相手の健康を気遣う、丁寧で温かみのある結びの言葉です。

↓以下のテンプレートは、親しい間柄に使ってみてください♡
〇〇様、ご無沙汰しております。
紅葉が盛りを過ぎ、木枯らしが吹き始める頃となりました。〇〇様におかれましては、冬支度など進めてお変わりなくお過ごしでしょうか。
小春日和のような穏やかな日もありますが、朝晩の冷え込みは格別です。どうぞ体調を崩されませんよう、ご自愛ください。
〇〇様
七五三の子供たちの賑やかな声に、季節の移ろいを感じる今日この頃です。いかがお過ごしでしょうか。
日脚もめっきり短くなり、吐く息が白くなる日も増えてまいりました。 これから本格的な寒さに向かいますが、どうぞ温かくしてお過ごしください。また近いうちにお目にかかれるのを楽しみにしております。
11月下旬に使える挨拶文
11月下旬は、秋が終わりを告げ、本格的な冬の寒さが目前に迫る時期です。木枯らしが吹き、紅葉も終盤を迎え、景色は深まる冬の装いへと変化します。この時期の挨拶文では、「晩秋の名残」と「深まる寒さへの配慮」を表現し、相手の健康を気遣う温かい一言を添えることがポイントです。
時候の挨拶:「初冬の候」「落葉の候」「向寒の候」「小雪の候」。「深冷の候」は寒さが深まったことを強調したい場合に使います。
季節の話題:木枯らしの話題、初霜の便り、紅葉の終焉、山茶花(サザンカ)の開花、暖房器具や温かい鍋物など冬支度の話題、勤労感謝の日(11/23)に触れる話題。
気遣いの言葉:寒さが本格化する時期なので、体調管理への配慮が大切です。「向寒の折、ご自愛ください」や、「本格的な冬に備え、お体大切に」といった、冬への準備を意識させる温かい言葉を使いましょう。

ビジネス向け例文
ビジネスシーンでは、「初冬」や「霜寒(そうかん)」といった格式ある言葉を使い、日頃の感謝や相手の健康・発展を願う気持ちを丁寧に伝えます。

「霜寒(そうかん)の候」は11月から12月初めまで使用可。霜が降りて寒くなる頃です♡
書き出しの例文【漢語調:フォーマル】
ビジネス文書や目上の人に送る場合に適した、格式のある挨拶表現です。

「霜寒の候、皆様には一段とご健勝のことと拝察いたします。」
解説:霜が降りるほどの強い寒さを意味する「霜寒」を使った、この時期にふさわしい格式高い書き出しの挨拶です。
「初冬の候、貴社におかれましては、いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。」
解説:暦上の冬を迎え、これからますます発展されることを願う、一般的な書き出しです。
「落葉の候、貴社におかれましては益々のご発展をお祈り申し上げます。」
解説:木々の葉が落ちる秋を表現。落ち着いた雰囲気で目上の方への書き出しに適しています。
結びの例文【漢語調:フォーマル】

「向寒のみぎり、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。」
解説:寒さに向かうこの時期に、相手の事業の発展を強く願う、前向きな結びです。
「木枯らしの折、くれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます。」
解説:強い寒風が吹く時期に、相手の健康を気遣う気持ちを込めた結びです。
「落葉深まる季節、皆様のご健勝とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。」
解説:落葉の秋を季節感として入れつつ、健康と事業の発展を願う結びです。
書き出しの例文【口語調:カジュアル】
親しい間柄や社内メールでは、季節の情景や温かみのある言葉を選びましょう。

「朝夕の冷え込みが厳しくなり、暖かなストーブが恋しい季節となりました。」
解説:親近感がありつつも季節感を伝える温かい書き出しです。
「冬の気配がいっそう濃くなってまいりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:初冬の訪れを自然な言葉で表現した親しみやすい書き出しです。
「朝晩は冷え込む日が増えてまいりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:体調を気遣う挨拶文。親しみを込めて相手の近況を尋ねます。
結びの例文【口語調:カジュアル】

「日脚(ひあし)も短くなりましたが、どうぞ温かくして健やかにお過ごしください。」
解説:冬の始まりの情景を盛り込み、相手の健康を願う温かい結びの言葉です。
「これから本格的な寒さに向かいますので、体調を崩されませんようご自愛ください。」
解説:健康を第一に気遣う表現。メール文末に添えやすい定番の結びの言葉です。
「初冬を楽しみながら、充実した日々をお過ごしください。」
解説:初冬の楽しみを入れ、親近感のある温かい結びにしています。
プライベート向け例文
個人的な手紙やメッセージでは、寒さが深まる季節に温かい気持ちが伝わる言葉を選びましょう。
書き出しの例文

「吐く息も白くなり、冬の訪れを感じる頃ですが、〇〇さんお元気で過ごされていますか。」
解説:肌で感じる寒さを話題にすることで、共感を生み出す親しみやすい書き出しです。
「木々が葉を落とし、秋の終わりを感じる頃となりました。お変わりなくお過ごしでしょうか。」
解説:初冬への移ろいを表現し、落ち着いた雰囲気で相手の近況を尋ねる書き出しです。
結びの例文

「温かいお鍋が恋しい季節ですね。風邪など召されませんよう、ご自愛ください。」
解説:冬の食卓を話題にしつつ、相手の健康を気遣う温かい結びの言葉です。
「日に日に寒さがつのってまいりますが、〇〇さんにとって穏やかな冬となりますように。」
解説:本格的な寒さを前に、相手の幸せを静かに願う、心温まる結びの言葉です。
「晩秋の穏やかな日々を楽しみつつ、元気にお過ごしください。」
解説:季節感を盛り込みつつ、相手の健康を願う前向きな結びです。

↓以下のテンプレートは、親しい間柄に使ってみてください♡
〇〇様
木枯らしが身に染みる季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 日が暮れるのがめっきり早くなり、吐く息も白くなる今日この頃、〇〇様におかれましては、お風邪など召されていませんでしょうか。
寒い夜には、体を温め、どうぞ無理なくお過ごしください。本格的な冬の寒さに向かう折、引き続きご自愛くださいませ。
〇〇様
冬の気配が濃くなりましたね。お変わりなくお過ごしでしょうか。 暦の上では既に初冬ですが、時折訪れる小春日和の暖かさが心に染みる頃です。
〇〇様におかれましては、穏やかなひとときをお過ごしのことと存じます。 何かと気忙しくなる時節ですが、どうぞ体調にはご留意され、初冬をお過ごしください。
まとめ
11月は、晩秋と初冬の凛とした寒さが同居する季節の変わり目です。11月の挨拶は、日ごとに増す寒さへの気遣いと、日頃のねぎらいを伝える機会です。ビジネスシーンでもプライベートでも、心温まる一言は相手への印象を大きく高めます。
この記事では、11月上旬から下旬(初冬・向寒)に使える、季節の挨拶と例文を徹底的にご紹介します。フォーマルな漢語表現から、親しい相手に送るカジュアルな温かい一言まで幅広く解説。
「小春日和」「木枯らし」といった11月らしい情緒的な言葉を使い、読み手に気持ちが伝わるメッセージを届けましょう。本記事を参考に、あなたのメールや手紙にLINEに「温もり」を添えてみてください。