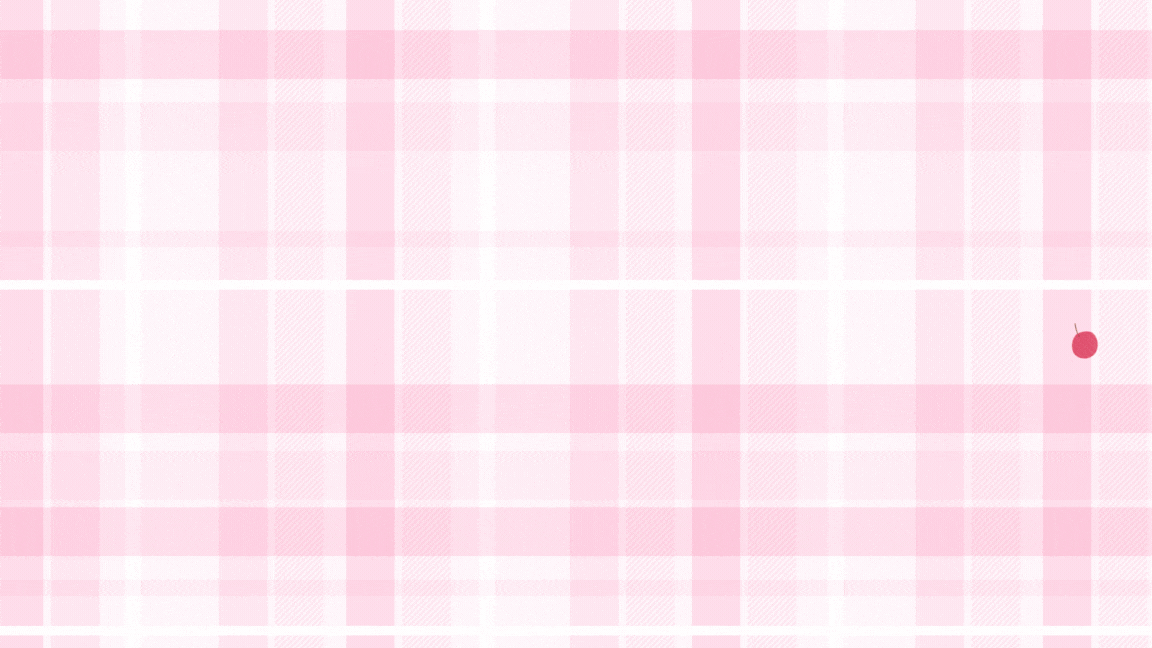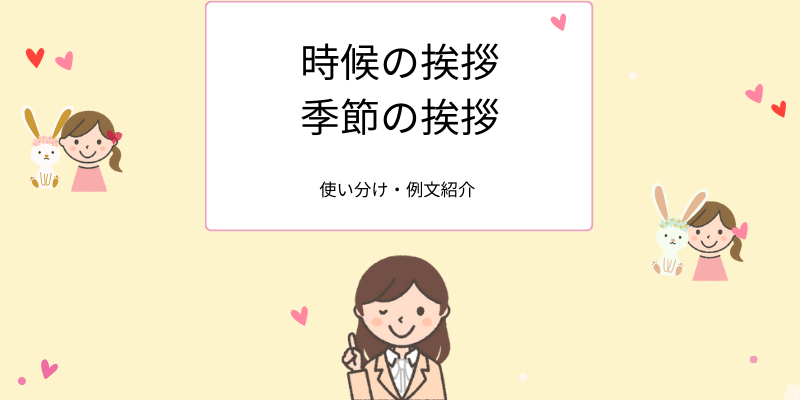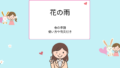「時候の挨拶」と「季節の挨拶」って、ビジネスメールや手紙でよく見かけるけど、何が違うんだろう…?いざ書こうとすると、どの言葉を選べばいいか迷いますよね。実はこれらは、相手への細やかな気遣いを伝える大切な要素です。この記事では、「時候の挨拶」と「季節の挨拶」の意味の違いから具体的な例文、ビジネスシーンでの適切な使い分けまで分かりやすく解説します。

挨拶文で自信を持って、気持ちの伝わる一文を添えましょう♡
時候の挨拶とは
時候の挨拶(じこうのあいさつ)とは、季節の移り変わりや天候に触れた挨拶の言葉のことです。特にビジネス文書や手紙の書き出しによく使われ、相手への思いやりや礼儀を示す表現として、日本では古くから親しまれています。
「時候の挨拶」は、季節感を伝えつつ、相手への配慮を込めた文章の冒頭として使われます。

↓時候の挨拶の特徴♡
時候の挨拶の特徴
・フォーマルな場面で用いられることが多い。
・書き言葉でやや形式的。
・手紙やビジネスメールの冒頭によく使われる。
・時候を表す言葉(例:立春の候、新緑の候)と相手の安否や健康を気遣う言葉(例:皆様におかれましてはご清祥のこととお慶び申し上げます)がセットになっていることが多くあります。

1月:厳寒の候、余寒の候
2月: 晩冬の候、向春の候
3月:早春の候、春暖の候
4月:陽春の候、桜花の候
5月:新緑の候、向暑の候
6月:梅雨の候、入梅の候
7月:盛夏の候、酷暑の候
8月:残暑の候、晩夏の候
9月:初秋の候、秋涼の候
10月:紅葉の候、清秋の候
11月:晩秋の候、向寒の候
12月:師走の候、歳末の候
近年では、形式ばった表現だけでなく、「日ごとに春めいてまいりました」といった親しみやすい文章もよく使われており、特にビジネスメールやカジュアルなやり取りでは、やわらかい言い回しが好まれる傾向にあります。
季節の挨拶とは
季節の挨拶とは、その季節の風物や気候にちなんだ、相手を気遣う挨拶の言葉のことです。
「最近暖かくなってきましたね」「桜が見頃の季節になりました」など、日常的な言葉で季節感や相手への思いやりを表す表現です。

↓季節の挨拶の特徴♡
季節の挨拶の特徴
・カジュアルな場面でも用いられる。
・会話に近い・親しみやすい表現。
・親しい間柄の手紙やメール、会話の導入などにも使われる。 時候の挨拶よりも自由な表現が多い。

1月:あけましておめでとうございます、今年もどうぞよろしくお願いいたします
2月:梅のつぼみが膨らみ始め、春の訪れを感じる頃となりました
3月:桜の開花が待ち遠しい季節となりました
4月:桜の花が咲き誇り、美しい季節となりました
5月:新緑が目にまぶしい季節となりました
6月:紫陽花の花が美しく咲く季節となりました
7月:夏空がまぶしい季節となりました
8月:連日厳しい暑さが続いておりますので、ご自愛ください
9月:秋風が心地よい季節となりました
10月:紅葉が美しい季節となりました
11月:木の葉が色づき、深まる秋を感じる頃となりました
12月:寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください
メールや手紙の結びの一言としても、「季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください」「春とはいえ寒の戻りもございます。お体を大切にお過ごしください」と、季節に合わせた気遣いの言葉を添えると好印象です。
Q&Aまとめ|時候の挨拶・季節の挨拶に関するよくある疑問
ビジネスメールや手紙を書く際、「時候の挨拶」は必ず入れなければいけないのか?「季節の挨拶」だけで失礼にならないか?などの疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、時候の挨拶と季節の挨拶の違いや使い分け方、句読点の使い方、結びの挨拶との組み合わせ方など、実際の文面で悩みやすいポイントをQ&A形式でまとめました。文例を交えて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
「時候の挨拶」はメールや手紙に必ず使わないといけない?
時候の挨拶は必須ではありませんが、フォーマルな印象にしたい場合にはおすすめです。
必ずしも「時候の挨拶」を入れる必要はありませんが、特にビジネス文書やかしこまった場面では、文章の印象を柔らかくし、季節感を伝える効果があります。
フォーマルな手紙や目上の人に送るメールでは、「〇〇の候」などの形式的な書き出しが一般的です。一方、親しい間柄やカジュアルなメールであれば、省略しても失礼にはなりません。

↑時候の挨拶省略できますが、 場面に応じて使い分けるのがポイントです♡
日常のメールや親しい間柄なら「季節の挨拶」だけでもOKですか?
日常のメールや親しい相手への手紙では「季節の挨拶」だけでも十分丁寧です。たとえば「春らしい陽気になりましたね」や「桜が見頃を迎えていますね」といったやわらかい季節の挨拶は、ビジネスでもプライベートでも好印象になります。
「時候の挨拶を使うほど堅苦しくしたくない」「温かみを伝えたい」そんな時に季節の挨拶だけを使う方が自然です。

挨拶文で自信を持って、気持ちが伝わる一文を添えましょう♡
時候の挨拶の句読点の使い方は?
時候の挨拶には基本的に句読点を使わないのが、昔からの手紙マナーとされています。
たとえば、「春暖の候 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」
といったように、句点(。)、読点(、)を省くことでフォーマルになります。
ただし、現代のビジネスメールでは句読点を使っても問題ないという考え方も増えており、可読性を優先するケースもあります。手書きの手紙では句読点を控え、メールでは読みやすさを重視するなど、状況に合わせて使い分けましょう。
結びの挨拶との組み合わせ方は?
時候の挨拶や季節の挨拶を使ったら、結びの挨拶でも季節感や相手を気遣う言葉を添えると自然です。
たとえば、冒頭に「春暖の候」などを用いた場合、結びでは、
・「季節の変わり目でもございますので、ご自愛ください」
・「春の訪れとともに、ますますのご活躍をお祈り申し上げます」といったように、季節感と相手への配慮をつなげる一言が理想的です。
メールや手紙の印象は、冒頭と結びで決まるとも言われています。バランスのとれた挨拶で、丁寧な印象にしましょう。

バランスのとれた挨拶で、丁寧かつあたたかみのある文章に仕上げましょう♡
まとめ
時候の挨拶は、季節の移り変わりに応じて相手の健康や安否を気遣うフォーマルな挨拶です。主にビジネスメールや手紙で用いられ、丁寧になります。一方、季節の挨拶は、季節の話題に触れ、親しみや共感を伝える、よりカジュアルな挨拶です。親しい間柄でのコミュニケーションに適しています。
ビジネスシーンでは、相手との関係性や文書の目的に合わせて時候の挨拶を適切に使うことが、丁寧で配慮の行き届いた印象になります。参考にしてみてください。